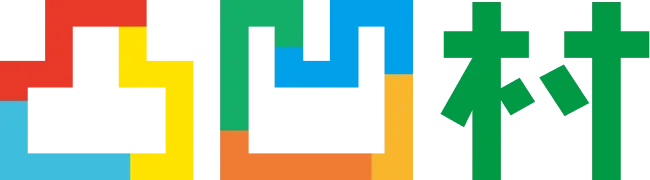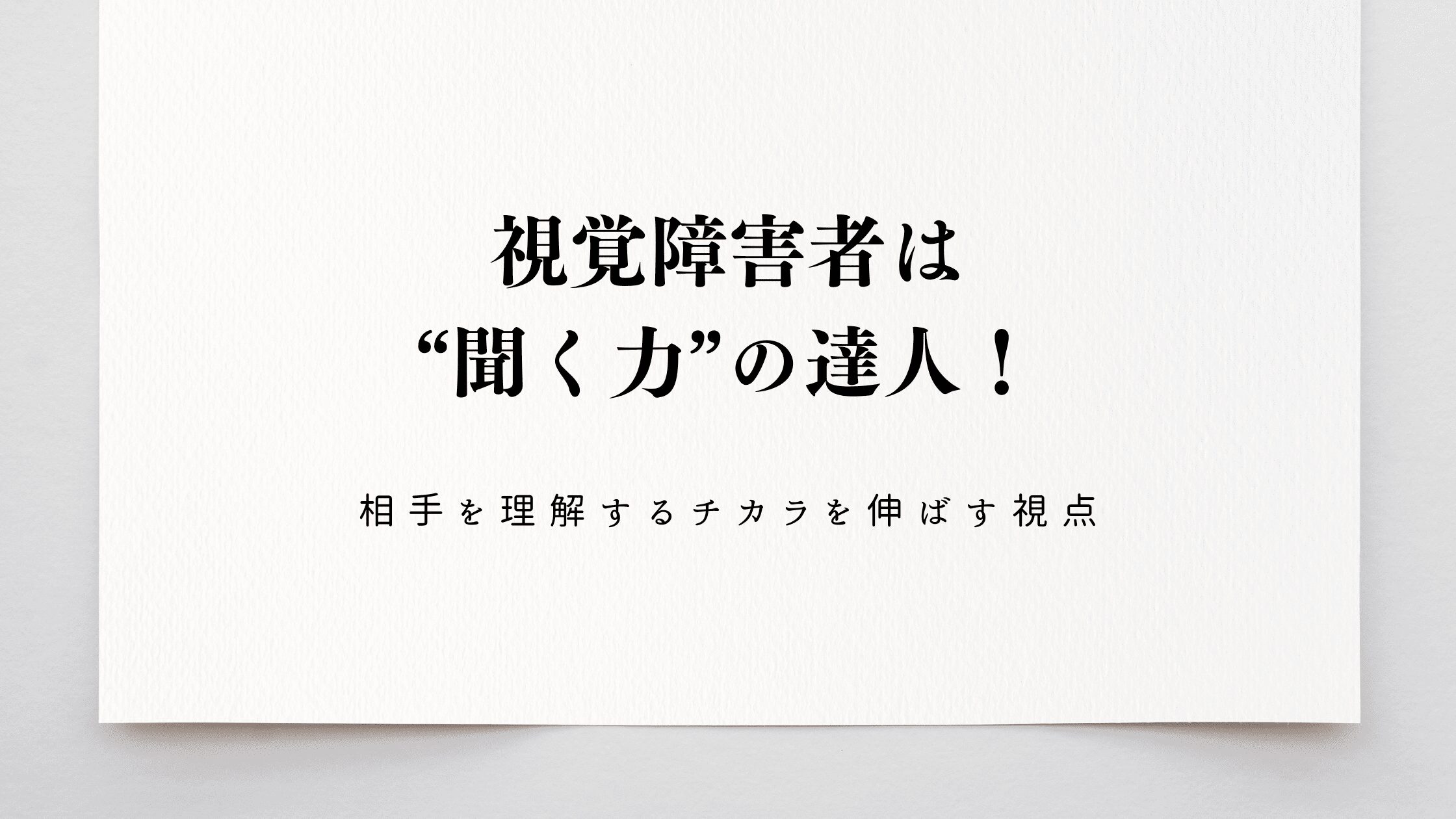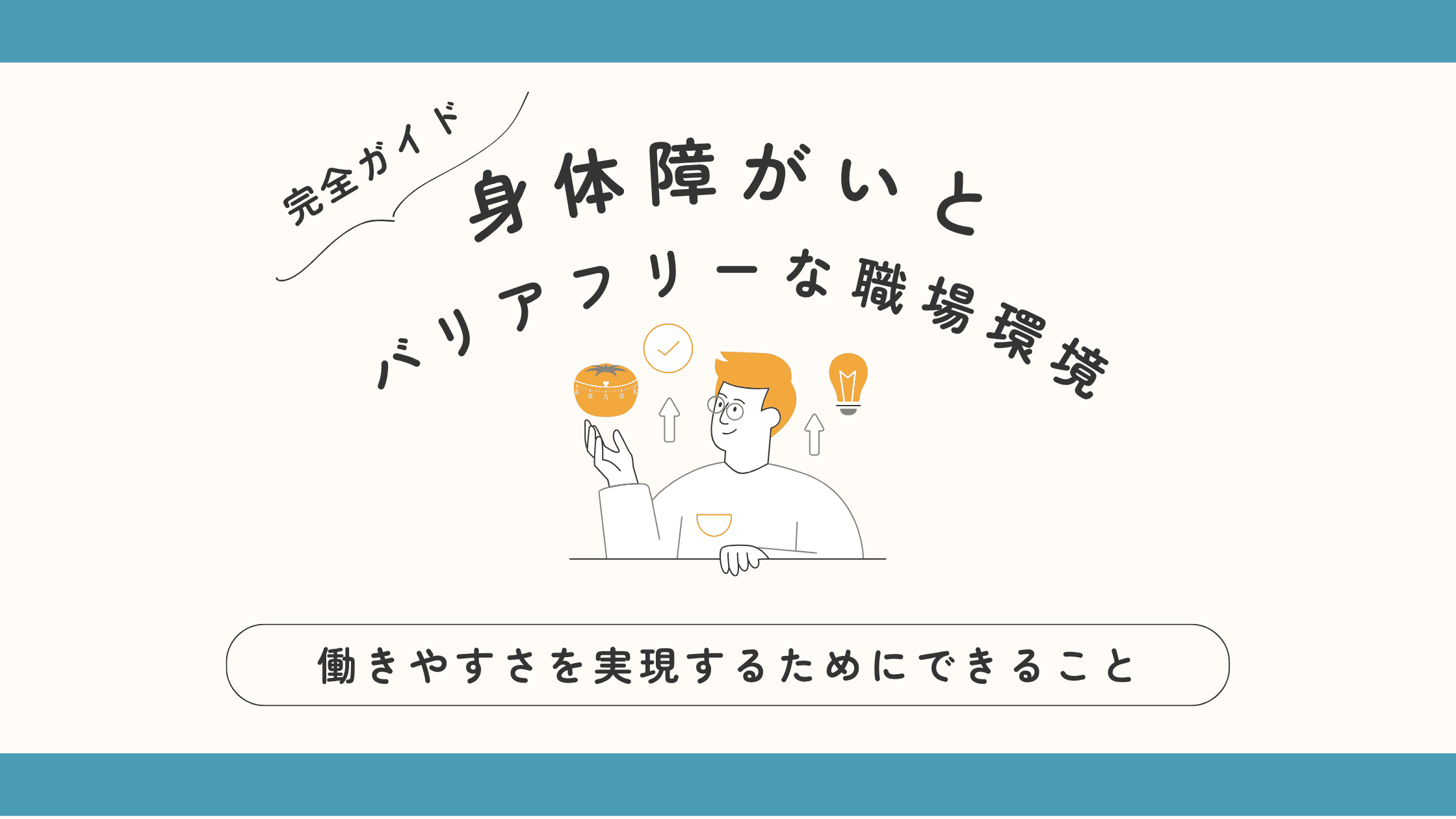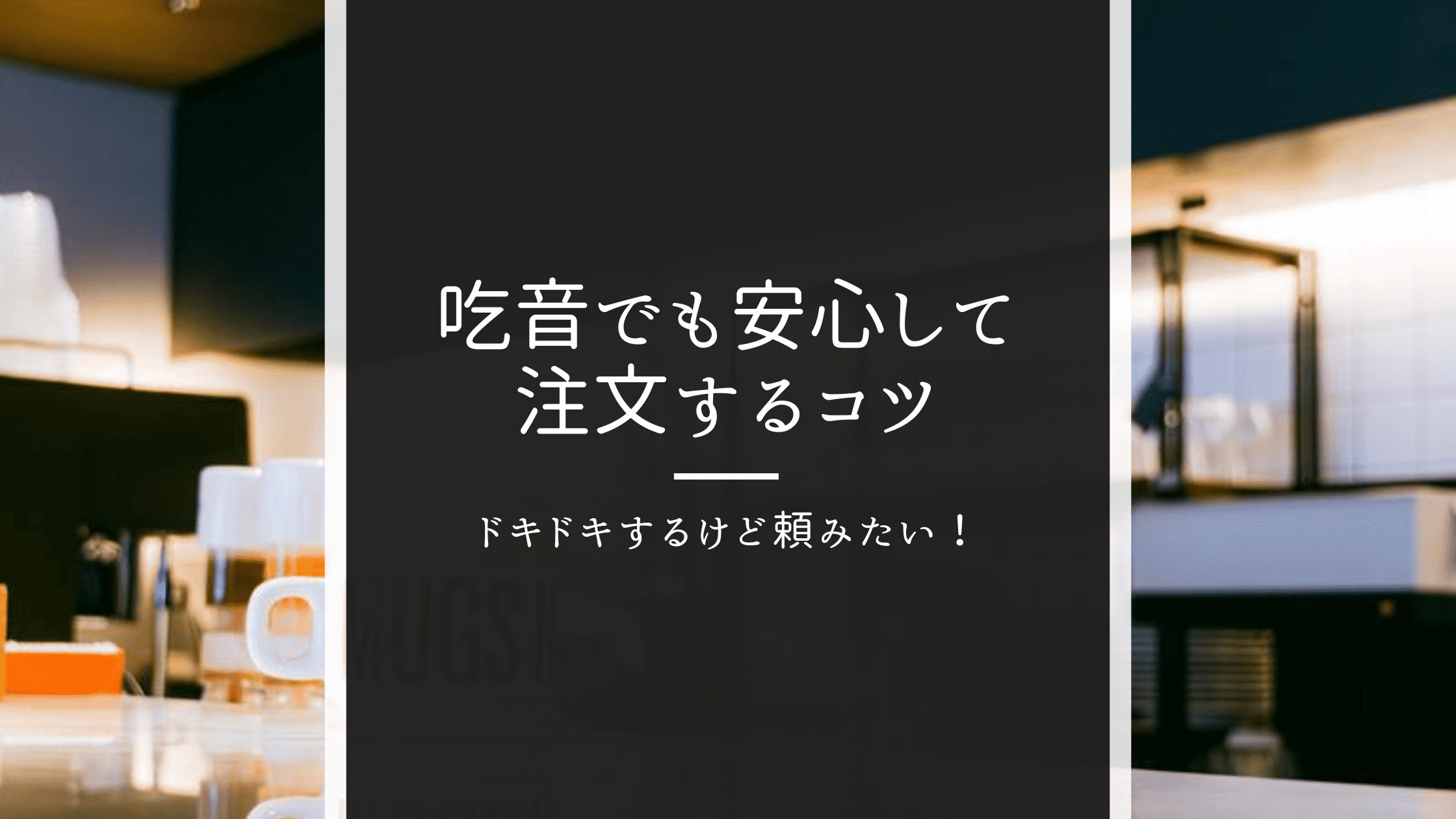介助を受けながら生活していると、「本当はこうしてほしい」「でも言いにくい」と感じる場面は少なくありません。
逆に介助者の立場でも、「どうサポートするのが良いのか分からない」「遠慮されているのでは」と悩むことがあります。
そんなとき役立つのが「アサーション」というコミュニケーションの方法です。
この記事では、介助者と当事者がお互いに尊重し合い、よりよい関係を築くためのコツを紹介します。
アサーションとは?介助関係に活かせる考え方

自分も相手も大切にするコミュニケーション
アサーションとは、「自分の気持ちや考えを大切にしながら、相手も尊重して伝える方法」です。
単に自己主張するのではなく、お互いが気持ちよくやりとりできることを目指します。
攻撃的でも受け身でもない「真ん中」
・攻撃的な伝え方…相手を傷つけてでも自分の主張を通す
・受け身な伝え方…相手を優先しすぎて自分を押し殺す
・アサーティブな伝え方…自分も相手も尊重する
介助関係は、相手への思いやりが強すぎて「受け身」になりがちですが、アサーションを意識するとバランスがとりやすくなります。
介助をお願いするときのアサーションの実践法

「事実・気持ち・提案」をセットで伝える
アサーションでは、「事実」「自分の気持ち」「どうしてほしいか」をセットで伝えるとスムーズです。
例)
「車椅子を押していただくときに少しスピードが速くて怖かったです。もう少しゆっくり進んでもらえると安心できます。」
これは相手を責めずに、自分の感じたことと希望を伝える方法です。
感謝を添えて伝える
お願いや修正をするとき、「いつも助けてもらってありがたいです」と感謝を言葉に添えると、お互いに前向きな気持ちになれます。
小さなことから練習する
「今日は右側に座ってくれると嬉しい」など、小さなお願いから伝えていくと、アサーションに慣れていけます。
介助を受ける側・する側の両方に大切な視点

受ける側に大切なこと
・「頼む=迷惑」ではなく「頼む=関係を築く一歩」と考える
・不安や遠慮をため込まず、少しずつ表現する
・自分の希望を伝えることで、相手も安心して介助できる
介助する側に大切なこと
・「何でもやってあげる」ではなく「どうしたいかを聞く」姿勢を持つ
・相手の選択や意思を尊重することが信頼につながる
・「ありがとう」を受けとめ、自分も無理をしすぎない
共通して意識したいこと
「お互いに支え合っている」という対等な感覚です。介助は一方的なものではなく、信頼と感謝で成り立つ関係性です。
アサーションを学べる実践的なリソース
アサーションは本や講座、動画などで具体的に学ぶことができます。
実際の会話例や実践方法を知ると理解が深まります。
- アサーショントレーニングの方法(スマカン)
- 書籍『改訂版 アサーション・トレーニング』平木典子著
- 【要約】夫婦・カップルのためのアサーション: 自分もパートナーも大切にする自己表現 【野末武義】(Youtube)
これらを参考にしながら、日常の介助場面で少しずつ実践してみると効果を感じやすいでしょう。
まとめ
介助者との関係は、ただの「助ける側」と「助けられる側」ではなく、対等なパートナーシップとして築いていけるものです。
アサーションを活用すれば、本音を伝えやすくなり、信頼や安心感が深まります。小さな一歩から始めることで、お互いにストレスを減らし、より心地よい介助関係を育むことができます。
「言いにくい」と感じたときこそ、アサーションの出番です。勇気を持って伝えることで、介助の時間がただのサポートではなく「一緒に生きるための大切な時間」に変わっていくでしょう。