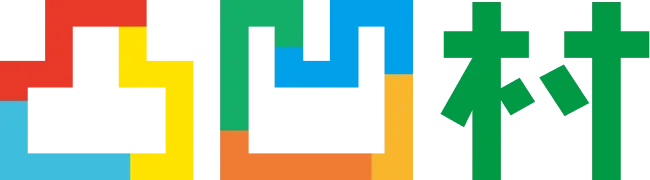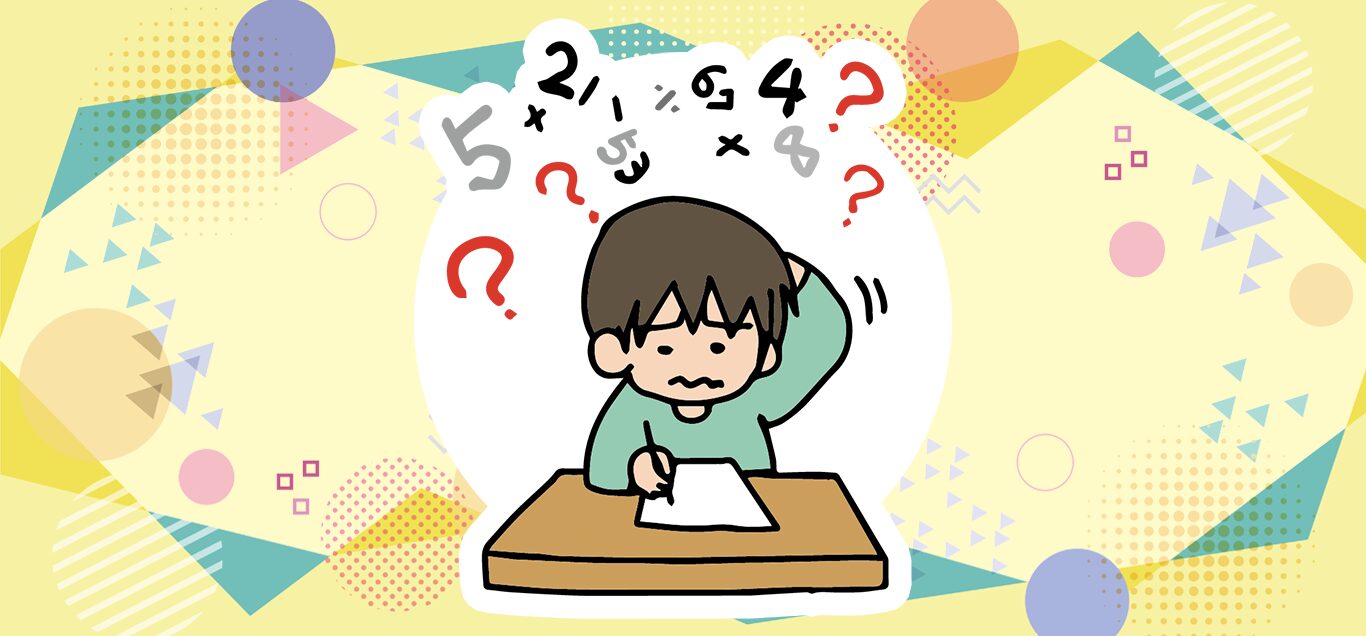山田火砂子さんは、30代で出産した長女が2歳の時に、知的障がいがあることがわかり、「どん底に突き落とされました」と振り返ります。泣いてばかりの日々を経て、開き直って生きようと決めてからの人生は、どのように変わったのでしょうか。
2歳の頃に知的障がいがあると診断
美樹さんが生まれたのは1963年。山田さんは将来を明るく夢見ていました。しかし、美樹さんが1歳になっても立つことができず、2歳の頃に知的障がいがあると診断されました。山田さんはその時、自分が「勉強もしないで威張りくさって天狗になっていた」と気づいたと述べます。
その後、山田さんは40代で映画プロデューサーに転身し、70代で実写監督デビューを果たしました。現在92歳の山田さんは、精力的に映画制作を続けており、2024年2月には新作『わたしのかあさん―天使の詩―』を完成させました。
山田火砂子さんが手がけた映画には、障がい児教育や福祉に関するものが多数あり、その背景には長女美樹さんの存在があります。彼女の人生は娘の誕生とともに一変し、その経験が彼女の映画作品に深く刻まれています。
福祉制度が整っておらず、障がい基礎年金制度もない時代
「国は助けてくれないし、医者代も取られる。母親が子どもを抱えて海に飛び込むというような事件がたくさんあった。障がいがある人はその頃は勤めるところがないし、食べることもできないから、のたれ死にする人だっていた」
山田さんもしばらくは泣いてばかりの日々でした。「天まで泣いたよね」。電車に飛び込もうと思ったことさえあったといいます。でも、泣き疲れたころに「何が怖いのだろう」と考えると、娘の障がいを「恥ずかしい」と思っている自分に気づきました。「開き直って生きよう」。そう考え、少しずつ前を向けるようになっていきました。
当時流行していたミニスカートをはく
美樹さんが通い始めた養護学校へ送り迎えするとき、山田さんは当時流行していたミニスカートをはいていました。
まわりの母親たちは人に隠れるように目立たない格好をしていたが、山田さんには「まわりと違う子どもを生んだら何もしちゃいけないのか」との疑問がありました。友達から「なんで障がいのある子どもの親だけ昔風の格好してこなきゃいけないの。あんたがやらないと誰も着られないから、先頭切ってやってみなさいよ」とけしかけられたといいます。「ばかだから乗せられて。プールに行ったらおへそが見えるような水着を着た」と山田さんは振り返ります。
次第に周囲を変えていく
山田さんの行動が、次第に周囲を変えていきました。ある日、養護学校の先生から「あなたがここに来てから、お母さんたちのスカート丈がだんだん短くなってきた。良い傾向です」と言われたといいます。
しかし、あからさまな差別にはしばしば苦しめられました。ある時は、自宅の周囲には「バカ、バカ、ゴレス」と書かれていました。美樹さんが「1+1は5れす(です)」「1+3は5れす(です)」と答えると、それを嘲笑されたのです。
山田さんは黙ってはいませんでした。美樹さんを侮辱した子どもの母親に直接話しかけましたが、「うちの子じゃない」と否定され、小学校の校長にも会いに行きましたが、「学区域外です」と言われました。養護学校の母親たちにこの話をすると、「私の子だって、近所の公園に行けば中学生からも『おばけが来た』と言われるわ」と告げられました。
「共に生きる社会が欲しい」
「障がい児と健常児、分けることなく共に生きる社会が欲しい」と山田さんは願いました。彼女は自らの経験と読書から、障がい児福祉に関する考えを深めていきました。
ある日、宮城まり子さんが養護学校を講演で訪れました。歌手や俳優を経て肢体不自由児の養護施設「ねむの木学園」を設立した宮城さんの話を聞き、山田さんは「私も芸能界のはしくれで生きてきた人間。自分のできる方法で運動しよう」と考えました。
ただ、美樹さんと次女を育てながら仕事を続けるのは簡単ではありませんでした。上映会前に子ども2人を連れて電柱にポスターを張って歩いたり、広島ロケに子どもたちを連れていき、旅館で留守番をさせたり。
美樹さんはふらりといなくなってしまうことが多く、撮影用のトランシーバーを使って新宿の街中を探し回ったり、千葉まで夜中に迎えに行ったりもしました。「稼ぐのに追われて、必死になって働かなきゃいけなかった」という日々でした。