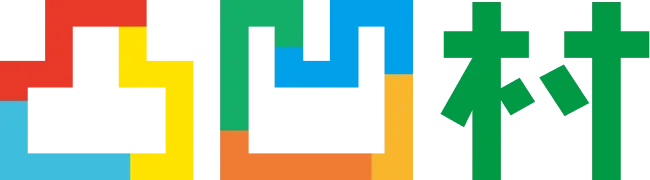「視覚障がいがあると料理は危ない」
「包丁や火を使うなんて無理」
こう思われがちですが、実はそんなことはありません。
視覚に頼らずとも、調理を安全かつ楽しく行うための道具や工夫は、近年急速に進化しています。
この記事では、視覚障がいを持つ方が自宅で料理をする際に安心して使えるサポートアイテムや、日々の調理を快適にするコツ、失敗しにくい環境づくりまでを解説します。
視覚に頼らない料理ってどういうこと?

他の感覚を活用した調理スタイル
視覚以外の感覚——特に聴覚・触覚・嗅覚——を活かすことで、調理の進行を把握できます。
フライパンが熱されたときの「パチパチ音」や、ニンニクの香ばしい香り、加熱した鍋の温度を触って確認するテクニックなど、感覚を研ぎ澄ませることで料理の“状態”を見極められるようになります。
参考動画
テクノロジーの進化が後押しに
音声ガイド付きのスケールや温度計、スマホアプリ「Be My Eyes」や「Seeing AI」「Envision AI」など、生活支援技術の進化によって、見えない部分を“聴く・伝える”ことが可能になりました。
調味料の識別、加熱状態の確認、レシピの読み上げなど、視覚の代替を担うアイテムが日常に溶け込んでいます。
参考動画
安全・快適なキッチン環境づくり

調理道具の定位置管理
使う道具は定位置に置きましょう。
たとえば、包丁は必ず同じ場所に戻し、棚には触って分かる「バンプドット」などを貼っておくことで、目に頼らず調理動線が安定します。
参考動画
火や刃物の“見える化”ならぬ“感じる化”
ガスコンロのつまみに触れる位置に印をつける、IHヒーターに音声操作やタイマーを組み合わせることで、誤作動や火傷リスクを減らせます。
包丁も、滑り止め付きのまな板や指ガードと併用することで、ケガのリスクを最小限に抑えられます。
事前準備が成功の鍵
具材や調味料はあらかじめ計量・仕分けしておきましょう。
すべての材料を手前に配置し、手順通りに並べておくだけで混乱を防げます。
実際に使える“神アイテム”5選

話すキッチンスケール(音声読み上げ)
視覚に頼らずに正確な計量ができるデジタルスケール。
指定の重さを読み上げてくれるため、砂糖・塩・小麦粉などの分量調整が安心です。
液体調味料が定量出せるさじかげん
一押しで10ccと15ccが出せる計量器。
決まった量の調味料が出せるので、味が濃くなったり薄くなったりすることがありません。
黒色まな板
弱視の方向け用。
例えば白い豆腐など、黒色のまな板だとコントラストで良く見えるようになります。
自助食器
縁が高く、食材を集めやすい構造。
片手で食事をすくいやすく、食べやすい設計です。
点字シール
家電スイッチや棚、調味料などに貼ることで、触っただけで操作や位置が判断できます。
安価かつ汎用性が高いのも魅力です。
参照:川崎市視覚障害者情報文化センター 視覚障害者用調理グッズ、coocpod news
視覚障がい者が料理を続けるためのコツ

成功体験を積み上げる
はじめは「卵かけご飯」「サラダ」「冷凍うどん」といった簡単なレシピから挑戦しましょう。
「できた!」という体験が自信を生み、次への意欲を高めてくれます。
習慣化と一貫性が鍵
使う調味料・道具の配置、レシピ手順を一定に保つことで、余計な混乱やストレスを回避できます。
毎日同じ流れをつくることが安心へつながります。
楽しむ気持ちを忘れずに
料理は義務ではなく“楽しみ”でもあります。
たまには香りクイズや食材当てゲームなどで、調理を遊びとしても取り入れてみましょう。
まとめ:道具と工夫で“料理できる自分”へ
視覚障がいがあっても、料理は十分に楽しむことができます。
必要なのは、少しの工夫と、安心を支える道具たち。
技術の進化とともに、料理の自由度は確実に広がっています。
最初から完璧を目指すのではなく、少しずつ「できる」ことを増やしていきましょう。
安心できる調理環境と、“できた”を積み重ねる日々が、あなたの暮らしに大きな自信と楽しさをもたらしてくれるはずです。
■参考動画
「全盲で一人暮らし?」火を起こす?手を切る?(料理編)
視覚障害弱視の「料理あるある」てんこ盛
視覚に障害があっても作れる!おすすめレシピ3選
関連記事