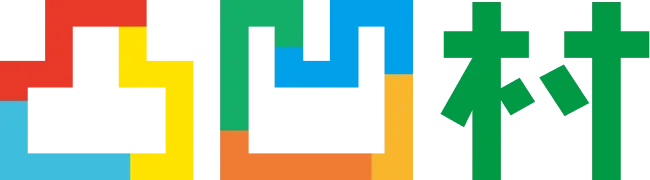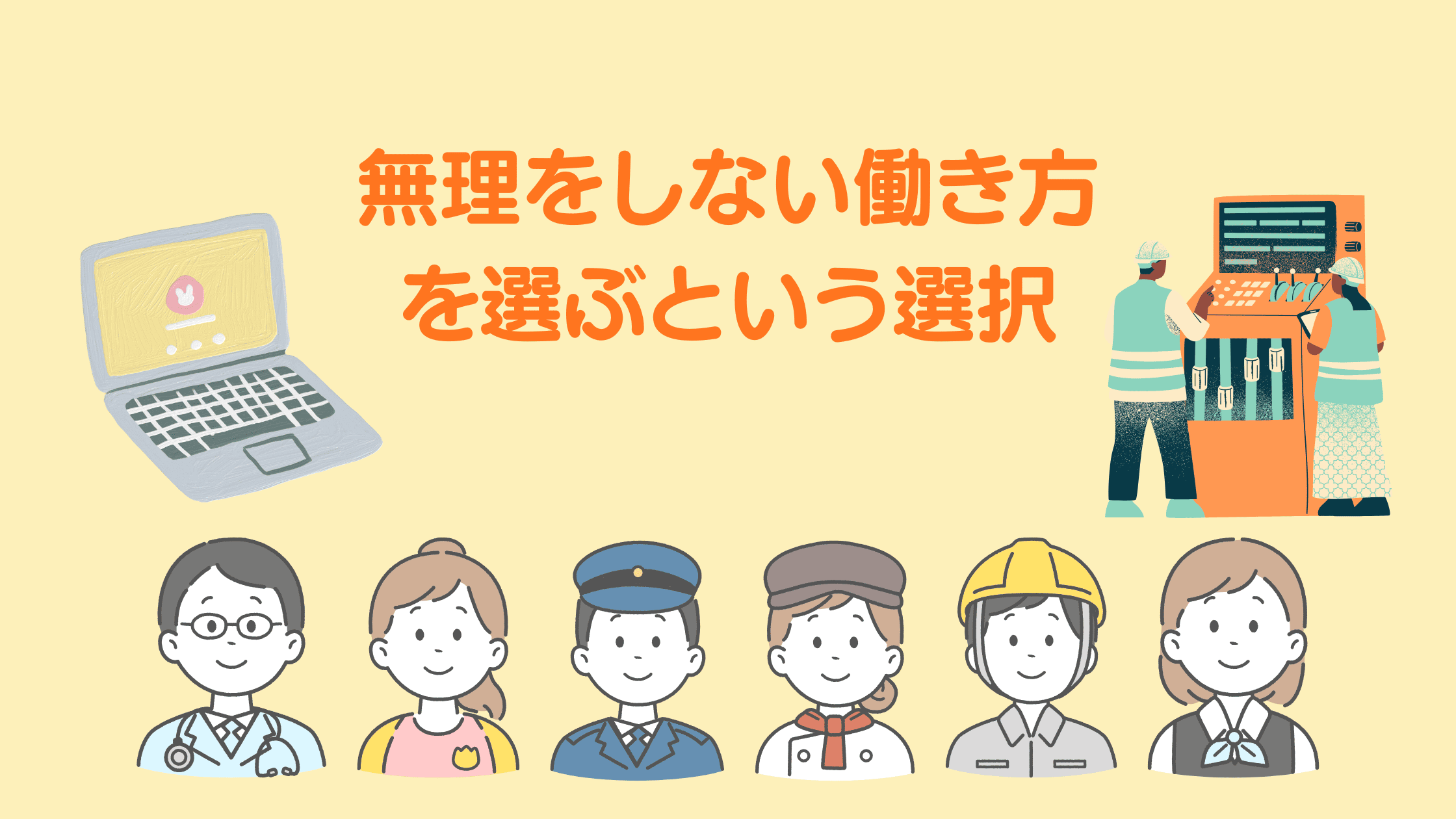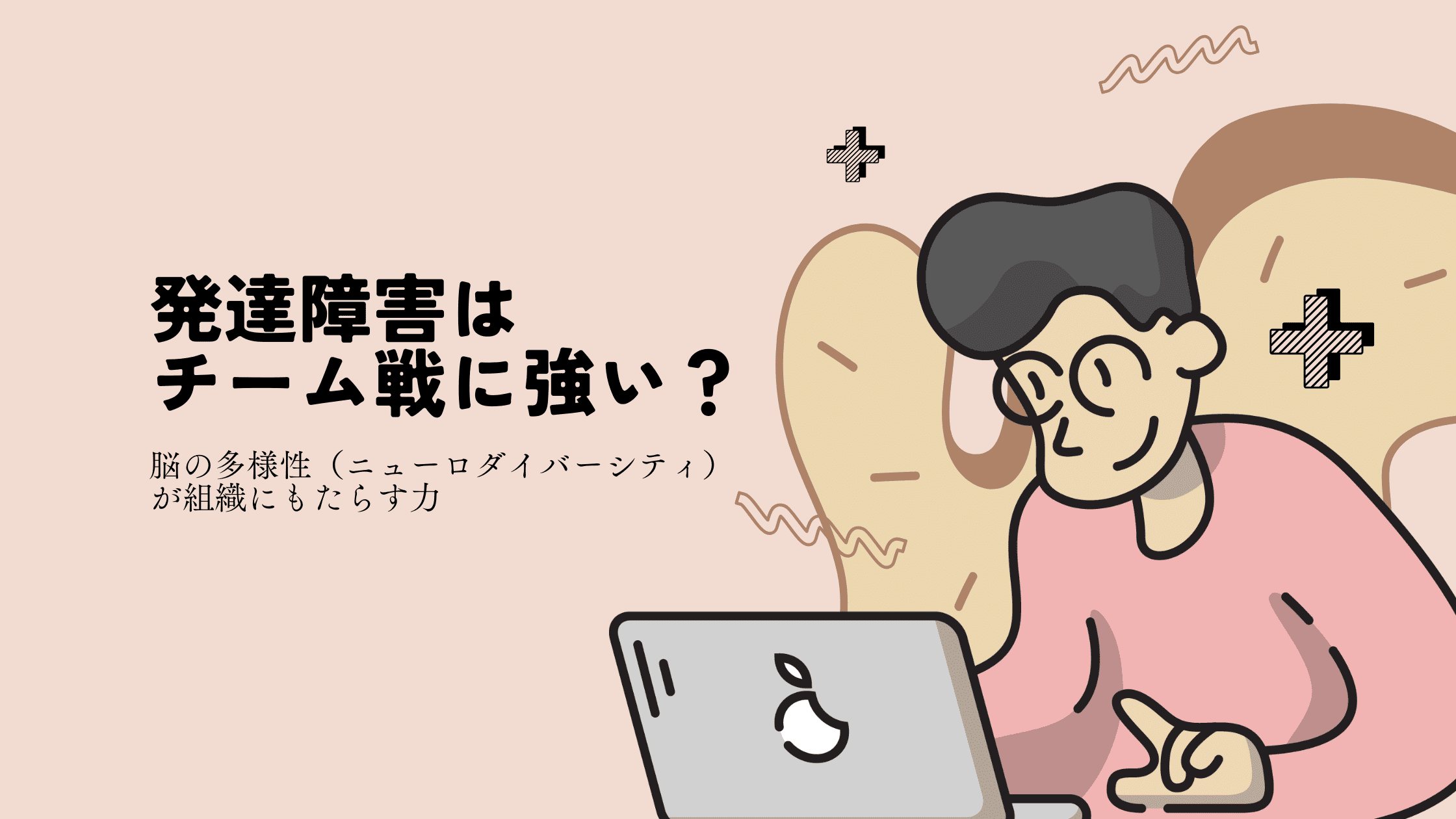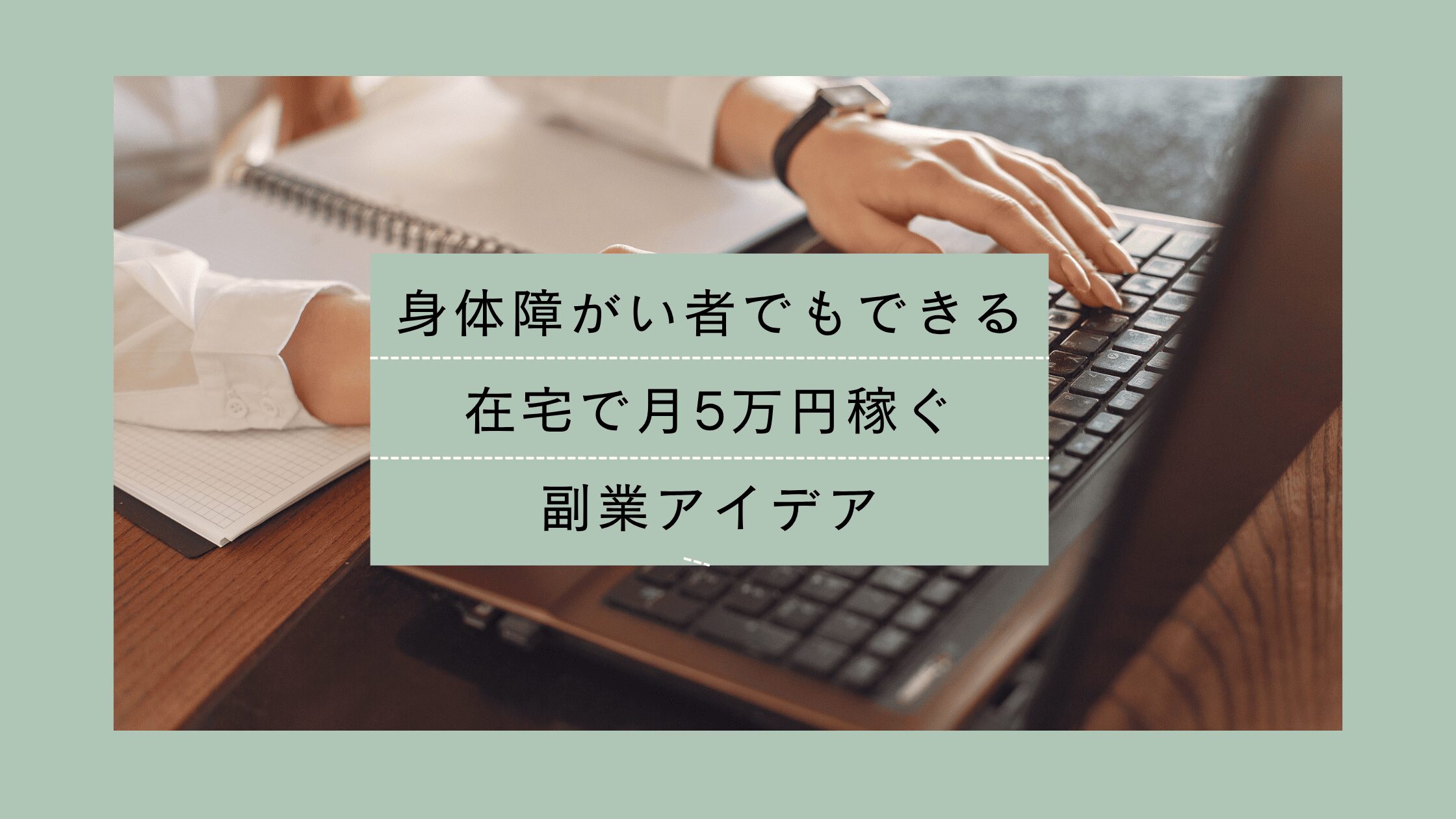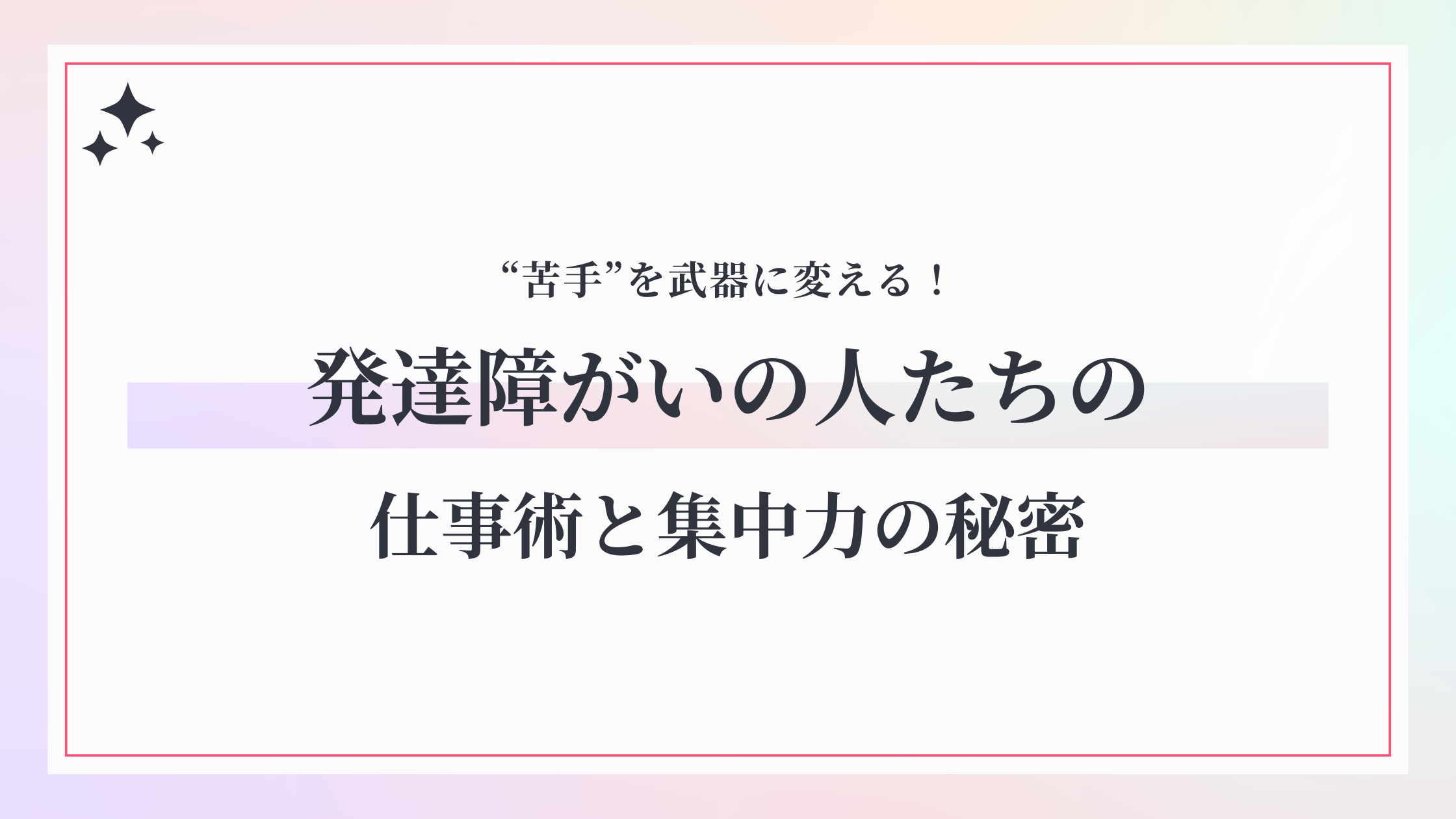日本では「バリアフリー」「障がい者雇用促進」といった言葉が当たり前になっていますが、世界の先進国やアジアの国々と比べたときに、どこが優れていて、どこに課題が残されているのでしょうか。
特に身体障がいを持つ人々の支援・社会参加という視点から、制度・就労・暮らし・権利保障など多角的に見ていきます。
日本の支援制度の概要と歴史的背景

日本における制度のスタートと変化
戦後まもなく、身体障がい者福祉法(旧法)が制定され、障がいを持つ人々への福祉支援の基盤が整備されました。
例えば、1960年代以降、障がい者自立生活運動なども生まれ、制度や支援のあり方に変化が見られています。
障害者雇用促進法と法定雇用率制度の構図
日本には、一定規模以上の企業に身体・知的・精神障がいを持つ人の雇用を義務付ける法定雇用率制度があります。
最近では2026年7月から民間企業の障がい者雇用率が 2.7% に引き上げられる予定です。
制度の枠組みと国際的な流れ
国連の 障害者権利条約(CRPD)を受けて、「障がい=個人の問題」から「障がい=社会のバリアによるもの」という社会モデルへの転換が世界的に進んでいます。
日本でもその動きが出ていますが、制度設計には医療・リハビリ重視の「医学モデル」の影響が根強いとの指摘があります。
世界との比較から見えた日本の強みと弱み

強み:従来制度の整備と社会的認知
日本には身体障がい者に対する福祉制度、障がい者手帳・等級制度、障がい者雇用義務などの制度が比較的早期に整っており、ある種の「制度基盤」が存在している点は強みといえます。
例えば、「Japan: People With Disabilities」では障がい者支援制度の概要が紹介されています。
弱み:就労・社会参加の実態と制度適用のギャップ
制度はあっても実際の社会参加や就労の実績では、他の先進国と比べて「対象範囲」「参加度」「選択肢の多様性」に課題があります。
例えば、日本の法定雇用率 2.3 %などは、フランス 6 %、ドイツ 5 %と比べると低く、支援対象も「より重度」の障がい者に偏っているという分析があります。
比較から浮かび上がる“アクセスと質”の差
障がいを持つ人が医療・福祉・地域生活サービスにアクセスする際、日本では「専門家が少ない」「相談窓口がばらばら」「地域格差がある」などの質的課題が報告されています。
例えば、身体障がい者と健常者の医療体験(patient experience)を比較した研究では、障がい者は「継続性」「地域対応」「サービスの包括性」の面で劣っていたことが示されています。
日本が抱える「身体障がい支援」の主要な課題

就労機会の限定と“形式的達成”の問題
法定雇用率があるにも関わらず、多くの企業がその達成に向けて「簡易作業」「別枠雇用」など限定的な雇用形態にとどまるという批判があります。
実際、2024年の報道でも「全企業のうち46%しか達成していない」とされ、数値上の達成だけでは実質的インクルージョンが進んでいないことが指摘されています。
障がいの幅・適用範囲の制限と対象格差
日本では支援の対象となる「障がい者」が法律上・制度上「一定の等級・レベル」を満たす必要があるケースが多く、他国と比べて“軽度障がい”や“支援が必要だが制度対象外”の層が見えにくくなっている点も課題とされています。
比較研究によれば、日本は「機能障がいがより深刻な人」に制度が寄っているという指摘があります。
地域間・サービス間の格差、生活支援の難しさ
地域によっては交通・建物・福祉サービスのバリアが未だ残っており、「障がいがあるから外出しづらい」「地域サービスが整っていない」といった声があります。
例えば「Top Most Disability-Friendly Countries Guide」では、日本は改善されつつあるが「アクセスに難あり」とも指摘されています。
今、世界が進めている支援の潮流と日本にとってのヒント

アンチ差別・合理的配慮を中心に据える動き
欧米では、雇用義務制度(クオータ制)から「合理的配慮」「差別禁止」を柱とした制度へと移行が進んでいます。
日本も2021年改正障害者雇用促進法で“合理的配慮”が企業義務化されましたが、実践に至るまでにはまだ課題があります。
Lived-experience(当事者経験)を政策・実践に活かすモデル
海外では障がい当事者自身が政策立案・支援サービス設計に参加することで、より実効的な支援が生まれています。
日本においても「当事者参画」の重要性が強調されており、支援の質を高める鍵となっています。
“インクルーシブ社会”を意識した環境整備・テクノロジー活用
アクセシビリティ(交通・建築・サービス)やICT/アシスティブテクノロジーの活用は、身体障がい者の自立と参加を促す上で、世界的にも重要なテーマです。
日本もそのトレンドに乗りながら、更なる整備が求められています。
身体障がい者支援をより良くするために、私たちにできること

支援制度を知り、自分ごととして捉える
まずは自分の住む地域・職場・学校でどのような支援制度があるかを把握することが大切です。
そして「制度を利用する・活用する」視点だけでなく、「制度を改善していく」視点も持つことが、持続可能な支援につながります。
発想を「支援される側」から「共に創る側」へ
身体障がいを持つ人を“支援される存在”とだけ捉えるのではなく、「共に働く」「共に暮らす」「共に支える」という視点を持つことで、社会の在り方が変わっていきます。
企業・地域・個人が“当事者中心”の視点を持つ
企業には、雇用率の達成以上に「働きやすい職場」「キャリアを描ける雇用」を問いかけたいです。
地域・学校・自治体には、「障がいがある人が“普通の生活”を送れる環境」という観点を強めていきましょう。
個人としても、「身体障がい者も当たり前に参加している世界」を意識した行動・理解が重要です。
まとめ:制度・実践・意識がそろってこそ“支援の質”が変わる
日本の身体障がい者支援には、制度的な基盤が整っているという面があります。
一方で、就労・地域参加・多様な障がい度合いへの対応・アクセス整備といった“質”の面では、世界と比べて改善の余地があります。
世界の潮流をヒントにしつつ、日本ならではの文化・社会資源を活かし、「障がいがあってもあっても自分らしく暮らせる・働ける」社会を目指していきましょう。