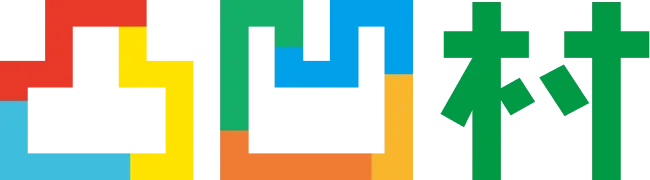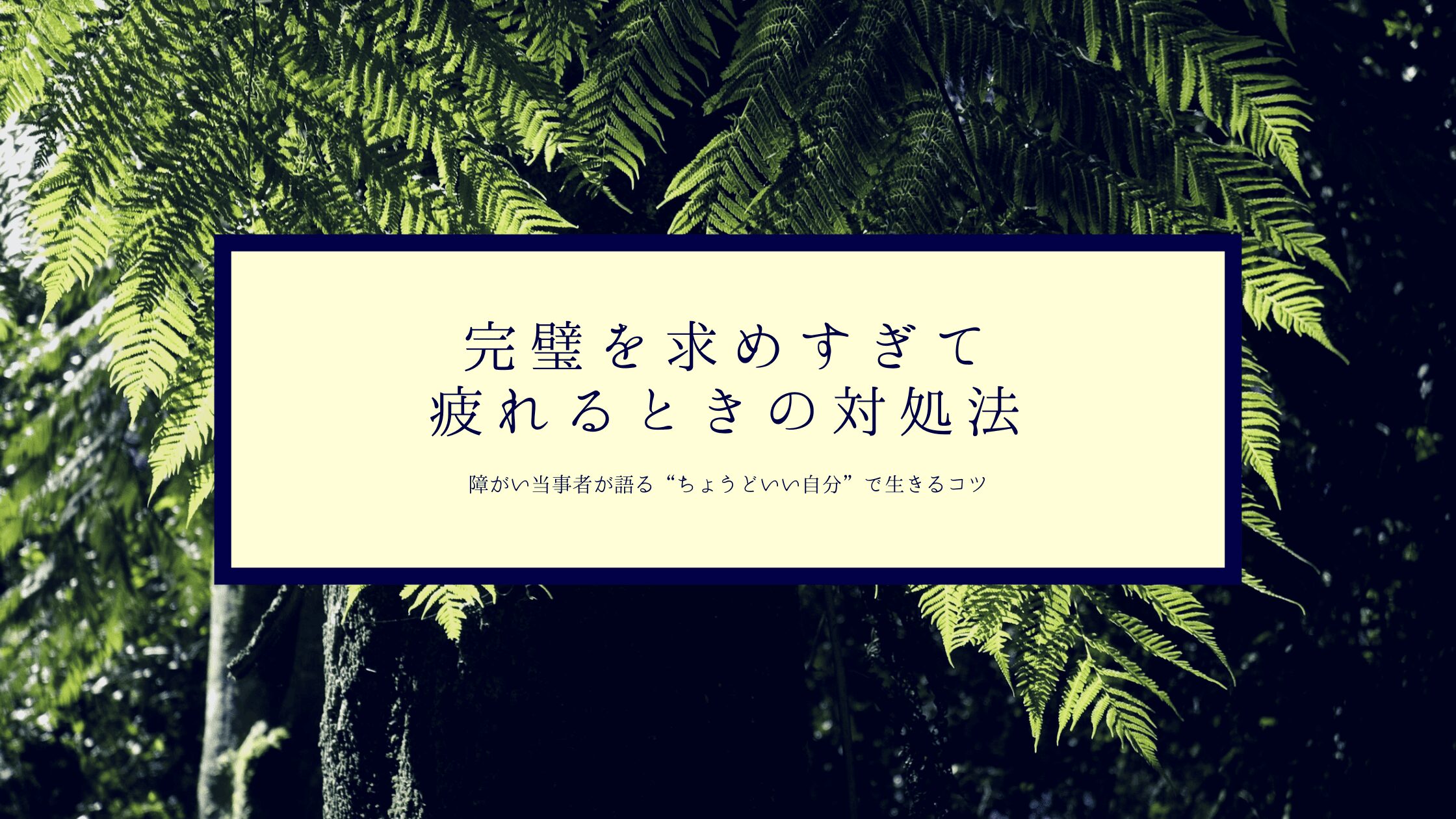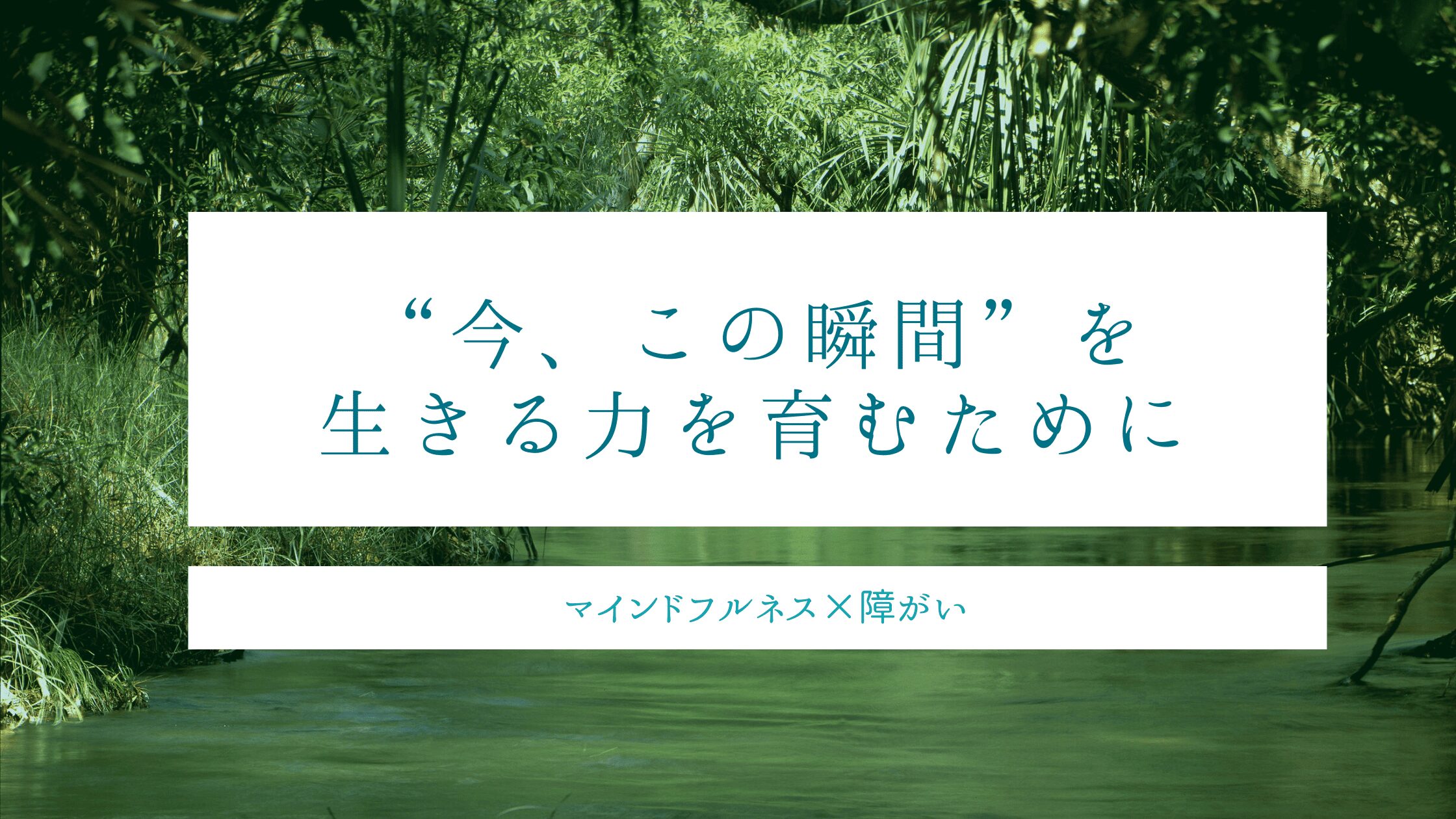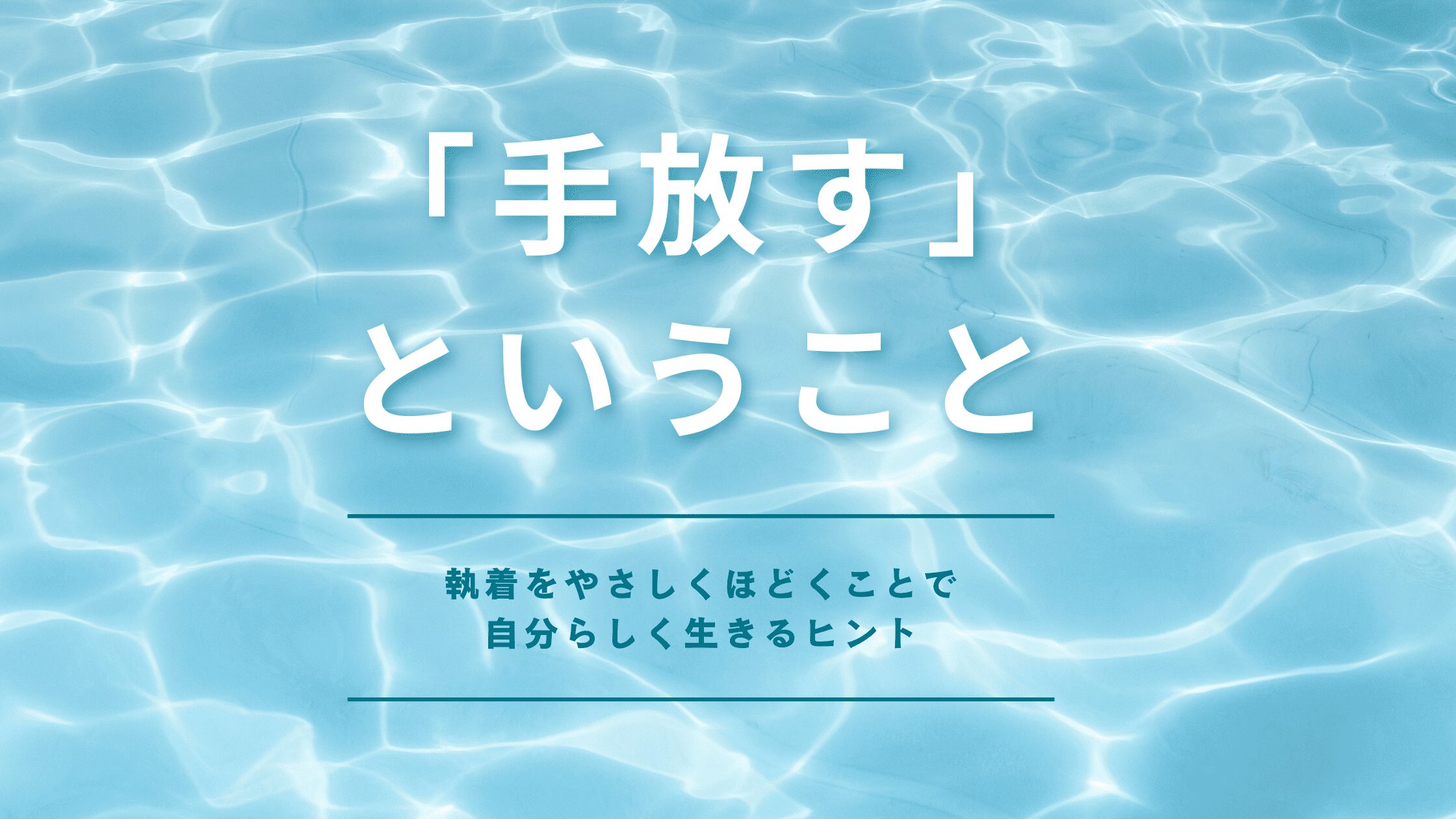「人に迷惑をかけてはいけない」
そう教えられて育った私たちは、つい「自分ひとりで頑張らなきゃ」と思ってしまいます。
でも、少し立ち止まって考えてみてください。
本当に、助けてもらうことは「悪いこと」なのでしょうか?
むしろ、「助けて」と言えることこそが、人を信じる勇気。
それは決して弱さではなく、前に進むための大切な力です。
この記事では、障がいのある人・ない人の垣根を越えて、「支え合うことの価値」と「助けてもらう勇気」がどんなに大切かを考えていきます。
「助けを求める」ことへの罪悪感を手放す

日本社会の“がまん文化”が生む孤立
日本では「我慢」「自己責任」「人に迷惑をかけない」が美徳とされがちです。
その結果、誰かに頼ることに罪悪感を持つ人が多いのです。
障がいのある人の中には、「サポートをお願いしたいけど、申し訳ない」と感じてしまう人も少なくありません。
しかし、助けを求めることは“他人に負担をかける”のではなく、“人と人をつなぐ”行為です。
たとえば、NHKのドキュメンタリー『バリバラ「助けてと言える社会に」』(https://www.nhk.jp/p/baribara/ts/D8M72R7P7Z/)では、
「助けて」と声を上げられない人が孤立していく現実が描かれています。
そこには、「弱さを隠す文化」が生み出す苦しみがありました。
助けを求めるのは「信頼の証」
もしあなたが「助けて」と言われたら、きっと“信頼されている”と感じるはずです。
だからこそ、自分が頼る側になったときも、相手を信じてお願いしていいのです。
「支えられること」は、「支えられる関係性がある」という証。
それは、人間関係の中で最もあたたかい循環のひとつです。
小さな「助けて」が社会を変える

手を差し出す側にも“成長”がある
「誰かを助ける」という行為には、“助ける側の成長”があります。
心理学者アルフレッド・アドラーも「人は他者への貢献によって幸福を感じる」と説いています。
障がい当事者が「助けて」と言うことによって、周囲の人が“支える経験”を得る。
それは社会全体に思いやりの連鎖を生み出します。
実際にあった“支え合い”のエピソード
東京メトロでは、視覚障がい者の方が駅員に「案内をお願いします」と声をかけると、
必ずスタッフが改札からホームまで安全に誘導してくれます。
(参考:https://www.tokyometro.jp/safety/barrierfree/support/index.html)
また、ろう者の方がスマホのメモアプリを使って店員に注文を伝えると、
店員が笑顔で応じ、「また来てくださいね」と返した——。
そんな“日常の中の支え合い”は、特別なことではなく、少しの勇気と優しさで実現できます。
SNSでも広がる「助け合い文化」
SNSでは、「#助けてって言っていい」「#一人じゃない」などのハッシュタグが広がっています。
X(旧Twitter)やInstagramでは、障がい当事者や支援者が日々の気づきを共有し、
「助けを求めることの大切さ」を発信しています。
このような情報発信が、孤立しがちな人たちにとって「声を上げてもいい」と思えるきっかけになっています。
「支え合う社会」はどうつくれるのか?

福祉=特別な人のため、ではない
「福祉」と聞くと、“自分には関係ない”と思う人も多いでしょう。
しかし、福祉とは「すべての人が安心して生きられる社会」のこと。
つまり、障がいがある人だけでなく、誰もが必要とする社会の基盤です。
内閣府の「共生社会づくり推進本部」(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/index.html)では、
「共に支え合い、誰もが自分らしく生きる社会」を目指す施策が進められています。
この動きの中心にあるのは、「支える人」と「支えられる人」を分けないという考え方です。
どちらの立場にもなる可能性があるからこそ、助け合いは“対等な関係”なのです。
日常の中でできる「支え合い」の一歩
支え合いは、特別なことをする必要はありません。
・席をゆずる
・困っている人に声をかける
・障がいのある同僚に「何か手伝えることある?」と聞く
こうした小さな行動が、社会全体をやさしく変えていきます。
やさしさは「制度」ではなく、「人の心」から始まります。
助けてもらう勇気が、誰かの希望になる
誰かが「助けて」と言えた瞬間、それを見た別の人が「自分も頼っていいんだ」と思える。
その連鎖が、社会をやさしく包み込みます。
「助けてもらう勇気」は、自分のためだけじゃなく、他の誰かのためにもなるのです。
おわりに:支え合うことで見える「本当の強さ」
人はひとりでは生きられません。
でも、それは「弱いから」ではなく、「人として自然なこと」だからです。
「助けてもらう勇気」は
「人を信じる力」
「自分を許す力」
そして「明日を生きる力」でもあります。
支え合う社会は、完璧な人が作るものではありません。
不器用でも、迷っても、お互いに手を差し伸べ合う心があれば十分です。
今日、ほんの少しでも誰かに「助けて」と言える勇気を持てたなら、
あなたはすでに“優しい社会”の一部になっています。
🔗参考リンク・動画
- 「助けて」という弱い言葉の強さ
ttps://www.shinmai.co.jp/feature/ayashiitv/2020/05/post-55.html - 東京メトロ バリアフリー案内
https://www.tokyometro.jp/safety/barrierfree/index.html - YouTube「「助けて」が言えないあなたへ〜発達障害の息子が教えてくれたこと〜」
https://youtu.be/PAfvQtzBA34?si=SUUWo5v_nXagdLNC