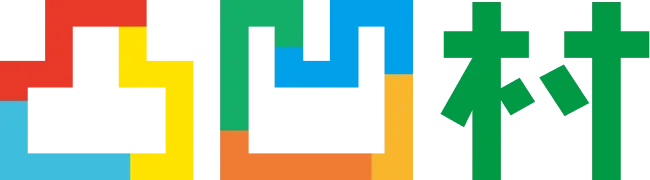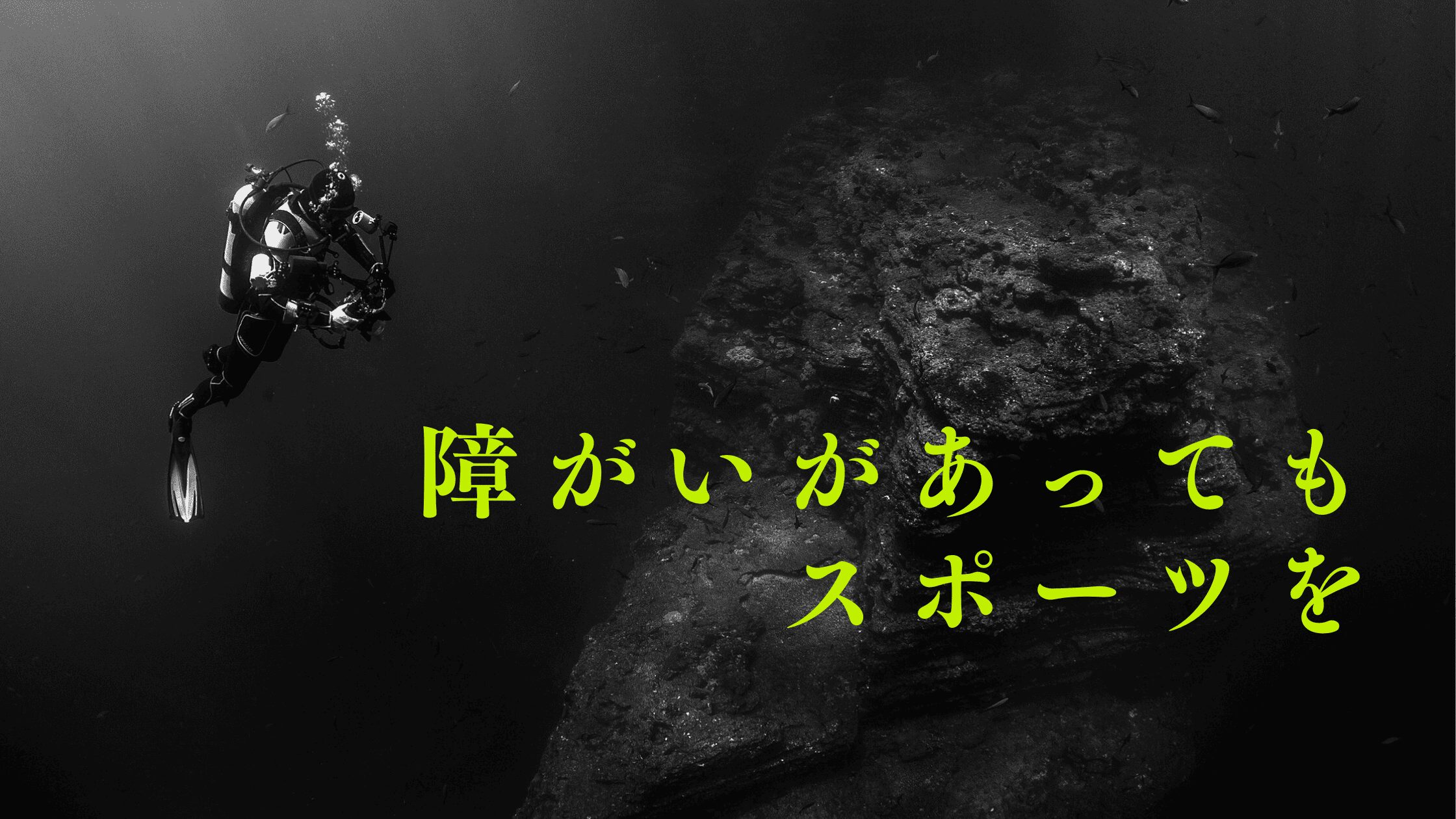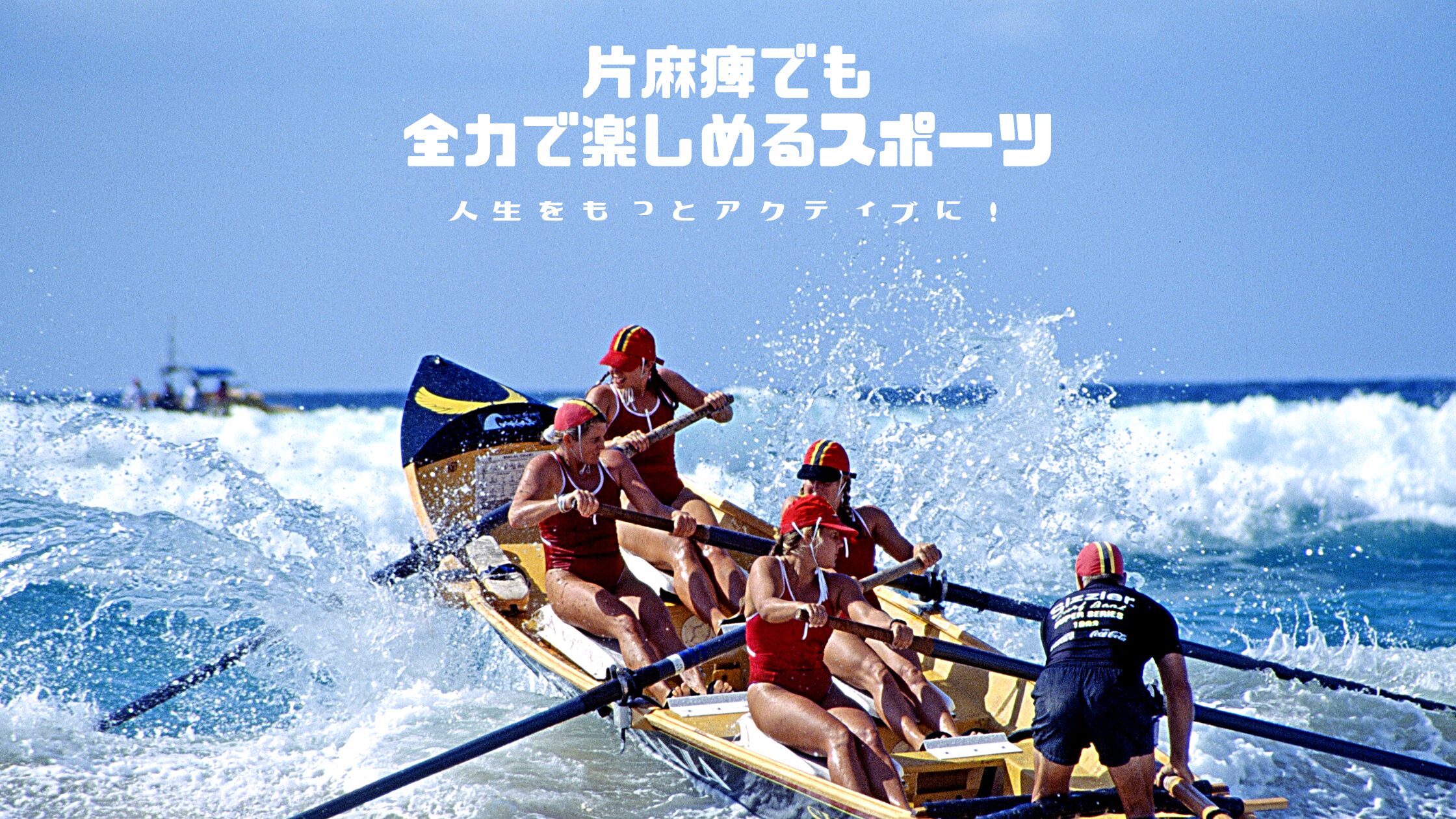私たちは毎日、何も意識せずに「呼吸」をしています。
けれど、ストレスや不安、体の不調が続くと、その呼吸は知らぬ間に浅く、速く、苦しくなっていくものです。
特に、障がいのある人にとっては、身体の動かしづらさや感覚の敏感さ、緊張のしやすさなどから、呼吸が乱れやすい傾向があります。
それは「がんばりすぎ」のサインでもあり、「少し休んでね」という体からのメッセージかもしれません。
呼吸は、心と体をつなぐ“橋”のようなもの。
深く穏やかな呼吸は、心を落ち着かせ、体を整え、前を向く力を取り戻すきっかけになります。
この記事では、障がいのある方でも無理なく実践できる呼吸法や、日常に取り入れるためのちょっとしたコツをご紹介します。
呼吸と障がい

呼吸の役割と普段見えにくい問題点
呼吸は、全身に酸素を届け、不要な二酸化炭素を排出するとともに、自律神経の調整にも関わる基本的な生理機能です。
日常では無意識に行われますが、障がいのある人にとっては「浅い呼吸」「息切れ」「胸式呼吸優位」などの傾向が表れやすく、その結果、疲労感や不調を招くことがあります。
たとえば、呼吸器疾患を持つ人たちを対象とした「呼吸リハビリテーション」の解説では、正しい呼吸法をトレーニングすることでQOL(生活の質)の向上が期待できるとされています。
参考リンク:呼吸リハビリテーションの目的と効果|正しい呼吸法でQOL
障がいの種類と呼吸への影響
障がいがあるということは、必ずしも呼吸に関係するわけではありませんが、次のようなケースでは呼吸が影響を受けやすくなります
- 筋力障がい・脊髄損傷などで胸郭や横隔膜の動きが制限され、深呼吸が難しい
- 呼吸器疾患(COPD、喘息など)を併発している場合、呼吸効率が落ちやすい
- 精神障がい(不安障がい、パニック障がいなど)により過呼吸傾向、呼吸の浅さ・速さに陥ることが多い(呼吸が交感神経優位になりやすい)
こうした背景を理解したうえで、呼吸法を取り入れることが「ただの健康法」以上の意味を持ちます。
呼吸法の種類と、その選び方

腹式呼吸(横隔膜呼吸)
腹式呼吸は、横隔膜を使って腹部を膨らませ・へこませるように息を吸って吐く方法です。「深い呼吸」を意識しやすく、自律神経の副交感神経を働かせる効果も期待できます。
YouTubeにもわかりやすい実演動画があります。
腹式呼吸の利点としては、肩こりや首の筋肉の緊張を軽くする効果、リラックス、そして呼吸の効率化が挙げられます。
参考リンク:厚生労働省 こころもメンテしよう こころと体のセルフケア、腹式呼吸の効果とは?メリットと正しい方法
478呼吸法(4-7-8 呼吸法)
478呼吸法は、吸う(4秒)→息を止める(7秒)→吐く(8秒)のリズムで行う方法です。ゆっくり吐く時間を長くすることで、自律神経を落ち着ける効果が期待されます。
呼吸のリズムを整えることで、緊張・不安の軽減、寝つきの改善などが見込まれます。
参考リンク:478呼吸法とは?心と身体をリラックスさせる4つの手順と注意点
参考動画
呼吸筋トレーニング/ストレッチ法
呼吸を補助する筋肉(肋間筋、腹横筋、横隔膜など)をストレッチや軽いトレーニングで動かすことで、呼吸能力を高めることができます。
YouTubeには「呼吸筋ストレッチ体操」という動画もあります。
呼吸と動きを組み合わせる方法
ヨガやピラティスでは呼吸と体の動きを連動させる方法が使われます。
特に初心者向けで呼吸法を重視したピラティス動画もあり、呼吸に意識を向けながら体を整えることができます。
障がい者が呼吸法を取り入れる際の工夫と注意点

無理をしないことが第一
呼吸法を取り入れようとした時、最初から「長時間・高負荷」でやろうとすると、逆に息苦しさや疲労を招く場合があります。
最初は1〜2分から始め、できれば座位・安定した姿勢で行うことが安全です。
補助道具やサポートを使う
呼吸が苦しい場合は、椅子・背もたれを使う、クッションを背中に置く、手すりを握るなどして、身体が支えられた状態で練習するのがよいです。
また、視覚障がいがある人は音声ガイドを活用する、手すり等を使って体を安定させながらゆったりやるなど工夫するとやりやすいでしょう。
呼吸法導入前に医師・理学療法士へ相談
呼吸器系の疾患や胸郭の可動性制限がある人は、誤った呼吸法をすると逆効果になることがあります。
特に心臓・肺に既往がある場合は、専門家の指導を受けることが望ましいです。
呼吸法を生活に取り入れるステップと習慣化のコツ

ステップ1:呼吸法を体験してみる
まずは短時間、軽く行うことから始めます。
例えば、夜寝る前の1〜2分や、休憩時間の合間などに取り入れてみましょう。
YouTube動画を見ながら真似してみるのも有効です。
ステップ2:振り返り・記録
呼吸法をしたあと、「どこが楽になったか」「どの姿勢でやりやすかったか」などを記録しておくと、自分に合った方法が見えてきます。
ステップ3:段階的に強化
慣れてきたら少しずつ時間を長くしたり、呼吸筋トレーニングを取り入れたりしてステップアップします。
ステップ4:他のケア習慣と組み合わせる
睡眠改善、ストレッチ、軽い運動、リラクゼーションと組み合わせると相乗効果があります。
特に呼吸法が睡眠品質を改善したという研究もあります。
まとめ:呼吸は「生きるリズム」
呼吸は、誰にでも与えられた「命のリズム」です。
しかし、障がいがあると、体の動きやストレス、生活リズムの乱れから、知らず知らずのうちにそのリズムが浅く・速く・不安定になってしまうことがあります。
そんなときこそ、「呼吸」に意識を向けてみることが大切です。
呼吸は、努力ではなく「寄り添い」で整うもの。
無理せず、焦らず、あなたのペースで呼吸を育てていきましょう。