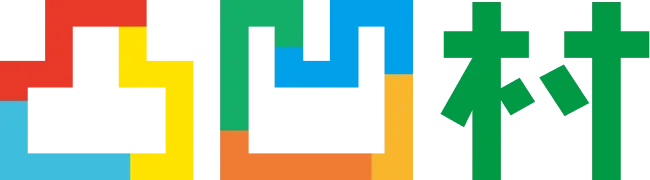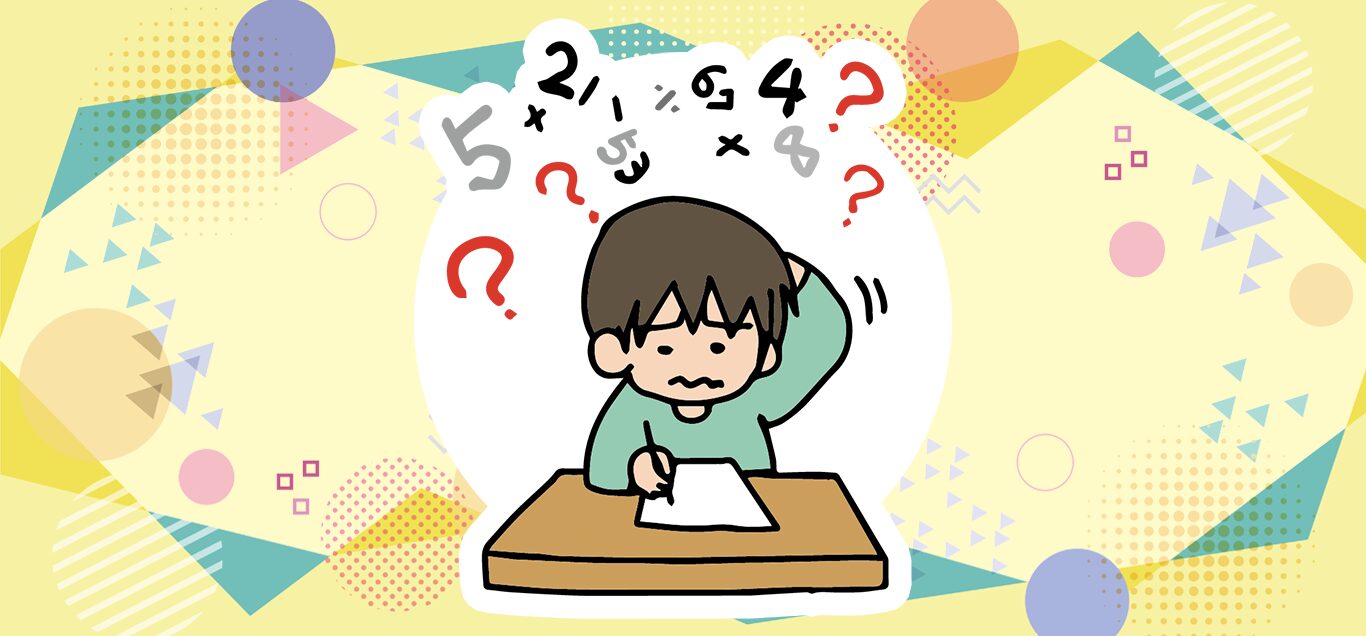障がい者の雇用は、一定数以上の従業員を抱える事業主にとって義務です。法定雇用率は、全従業員のうち身体や知的、精神障がい者の割合を示し、今年4月には2.3%から2.5%に引き上げられました。
これは、40人の従業員のうち1人が障がい者であることを意味します。そして、2026年には2.7%にさらに引き上げられる予定です。しかし、現状でも従来の2.3%でさえ、達成率は約50%にとどまります。達成できない場合は、納付金の支払いや行政指導、企業名の公表などのペナルティが課されますが、これらが改善に繋がるかは不透明です。
突然身体障がい者になってしまう
突然の障がいで職を失った濱田靖さん(58歳)は、神奈川県茅ヶ崎市に暮らしています。彼は肢体不自由で、身体障がい者手帳2級を所持しています。右半身がマヒしており、上肢は親指と人さし指しか動かせず、下肢はひざから下の感覚がほとんどありません。
彼の障がいは2004年9月に発生しました。茅ヶ崎市の病院で健康診断を受けている最中に、採血中に意識を失いました。目が覚めると、全身の筋肉が硬直しており、動けませんでした。妻に迎えに来てもらい、借りた車いすに乗って帰宅しましたが、玄関で再び昏倒し、翌朝まで意識が戻りませんでした。
「働く中で一番つらい」
濱田さんは療養のために実家がある佐賀県へ帰省し、医師から脳に小さな梗塞のような痕跡がたくさんあると告げられました。さらに、頸椎や脊髄の損傷も発覚しました。約1カ月半の入院と懸命なリハビリの末、杖をつけば歩けるまで回復しましたが、医療事故を主張しても健康診断を実施した病院側から認められず、民事訴訟でも敗訴に終わりました。
彼は自らの経験から、「ただ障がい者というだけで、周囲から『何もできない人』と見なされる。それが働く中で一番つらい」と語ります。
身体障がい者となってから一変
濱田さんはそれまで、特に大病を患った経験はありませんでした。高校卒業後、難関大学の受験で2年間浪人しましたが、合格せずに就職しました。何度か転職を経験し、30歳の時には接着剤や塗料を開発するベンチャー企業の立ち上げに携わりました。少人数だったため、営業や施工、新製品の研究など、多岐にわたる業務をこなしました。
激務と引き換えに事業は軌道に乗り、ピーク時の年収は約1500万円に達したといいます。しかし、経済的に恵まれた生活環境は、身体障がい者となってから一変しました。勤め先に事情を説明すると、すぐにリストラされ、退職金も出ず、生活のために貯金を切り崩す毎日を送りました。佐賀では障がい者向けの求人が少なかったため、神奈川の自宅へ戻り、ハローワークに通いました。
「何か自分にもできる仕事があるはず」
「体が不自由になったとはいえ、頭はハッキリしている。何か自分にもできる仕事があるはず、という思いが心の支えだった」と濱田さんは語ります。しかし、新しい職場は見つかりませんでした。企業が優先的に雇いたがるのは、受け入れが容易な軽度の障がい者であり、症状が比較的重い濱田さんはなかなか採用に至りませんでした。