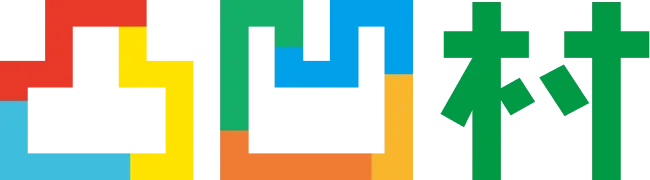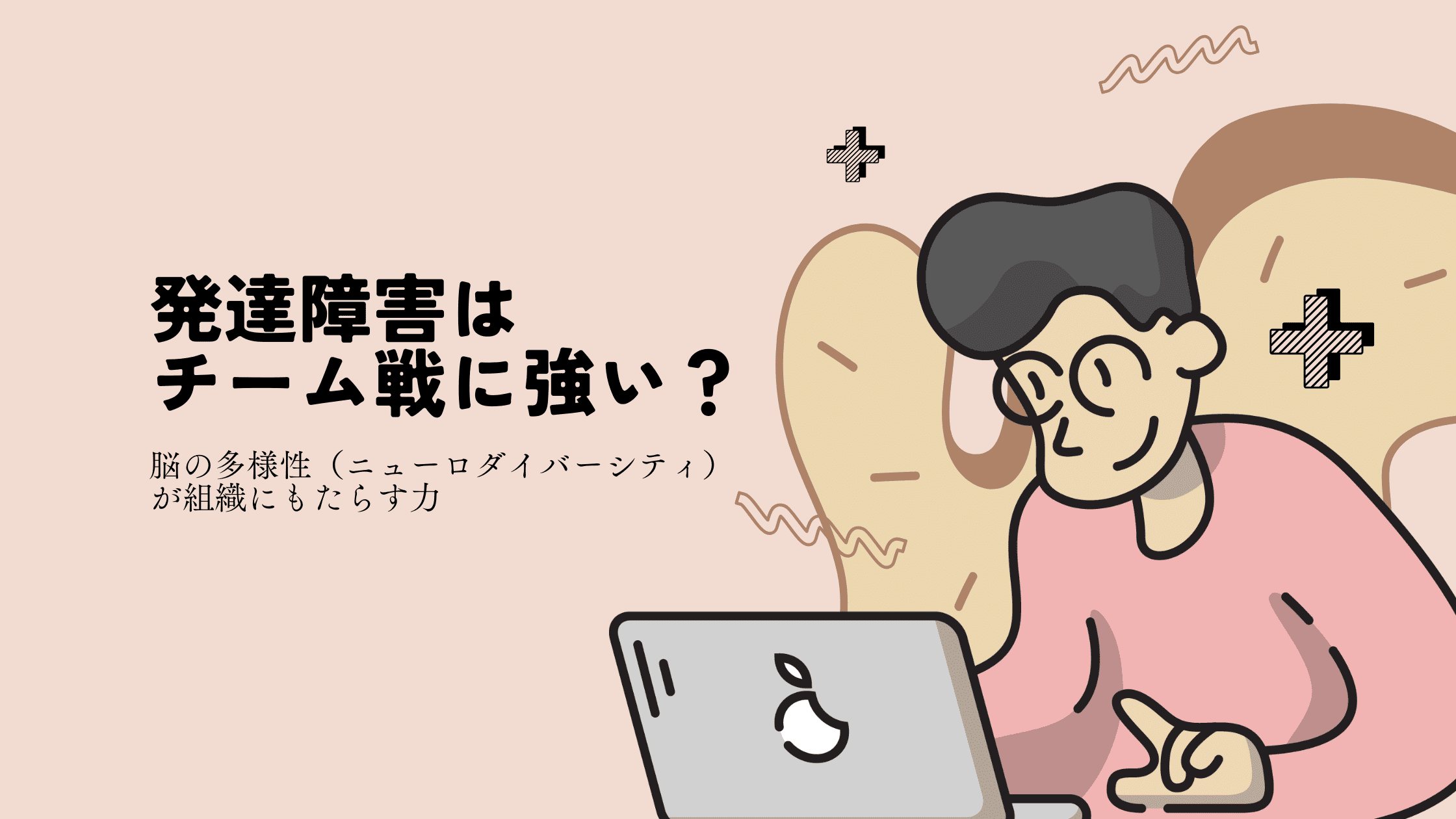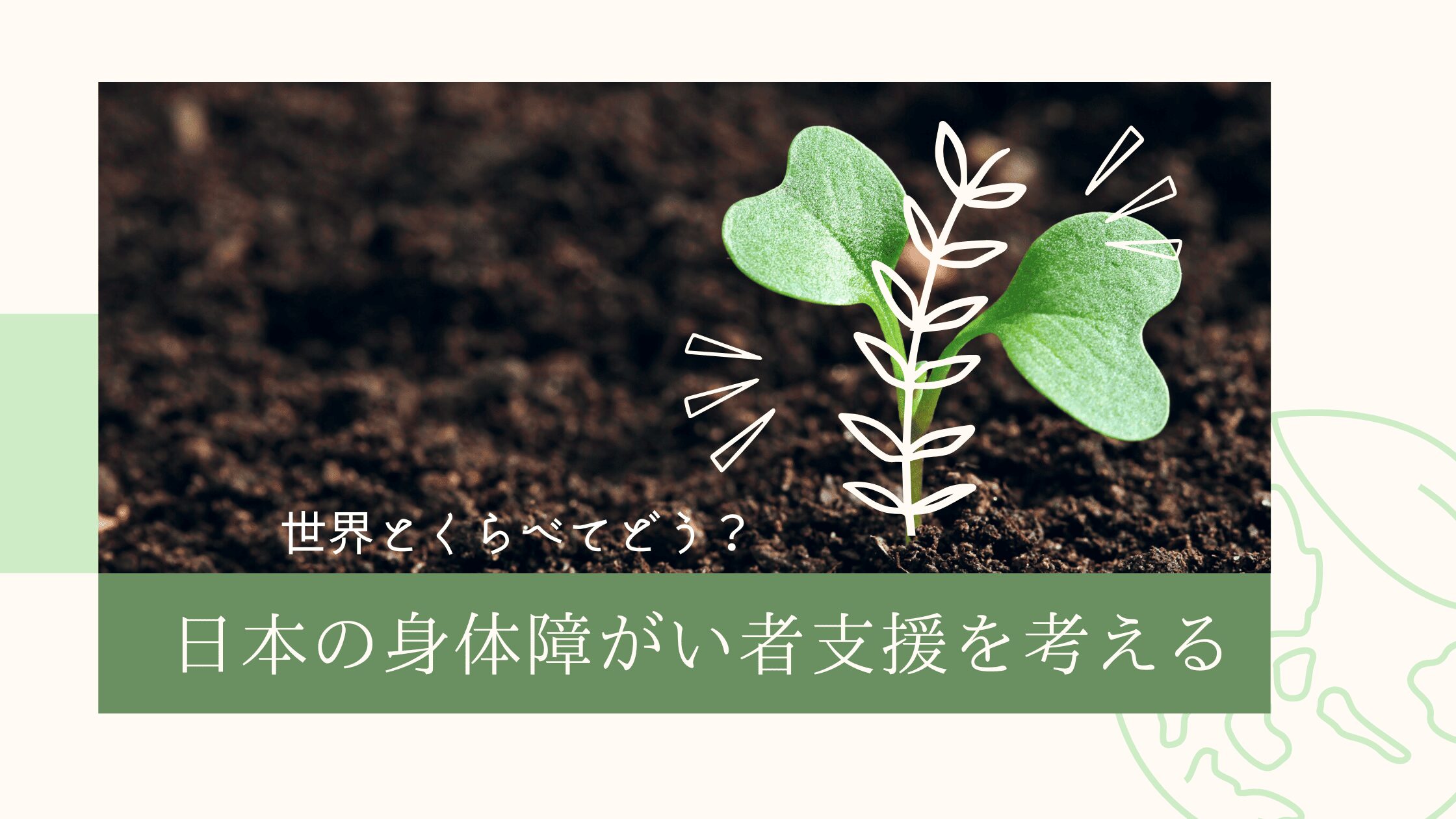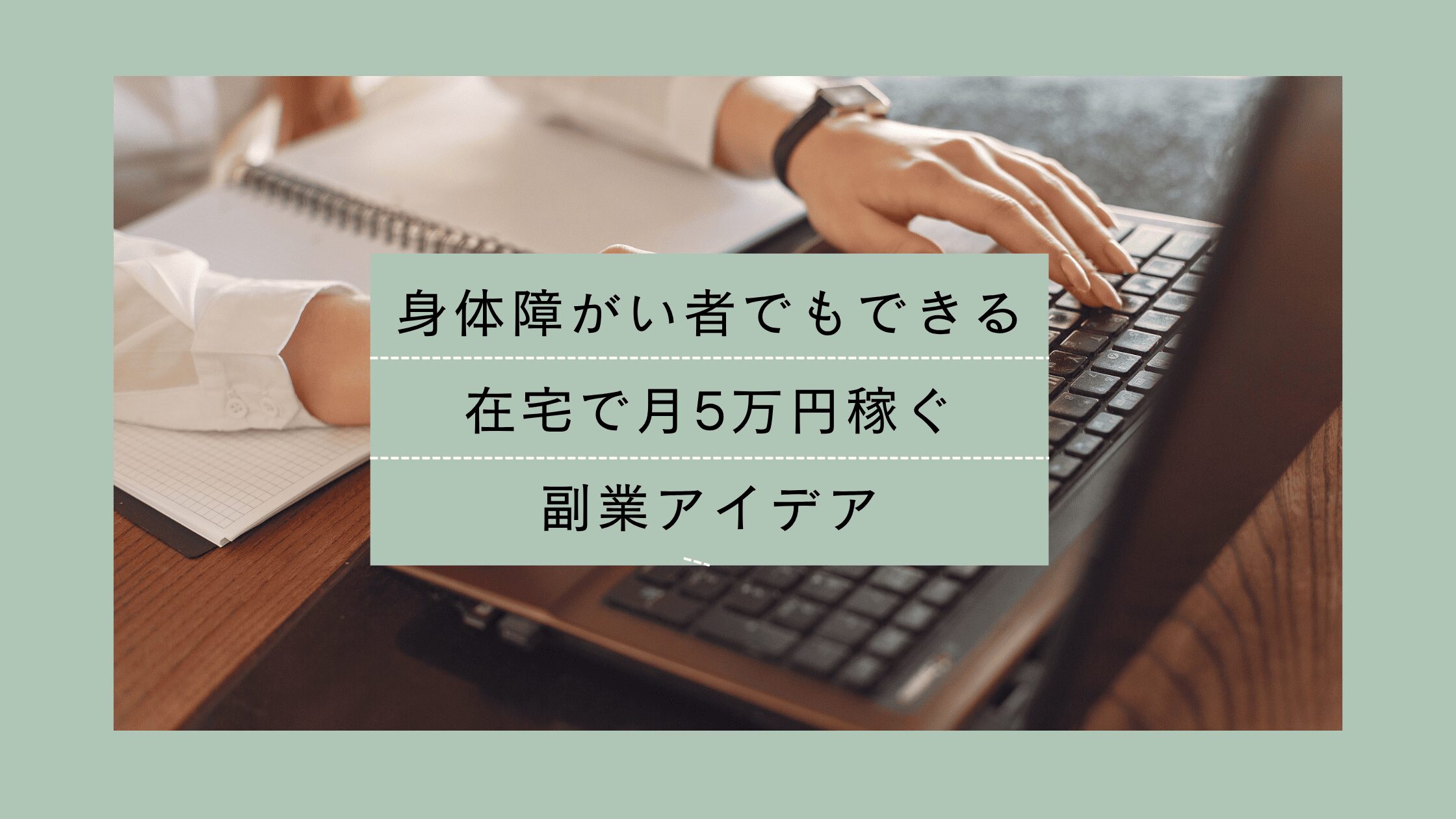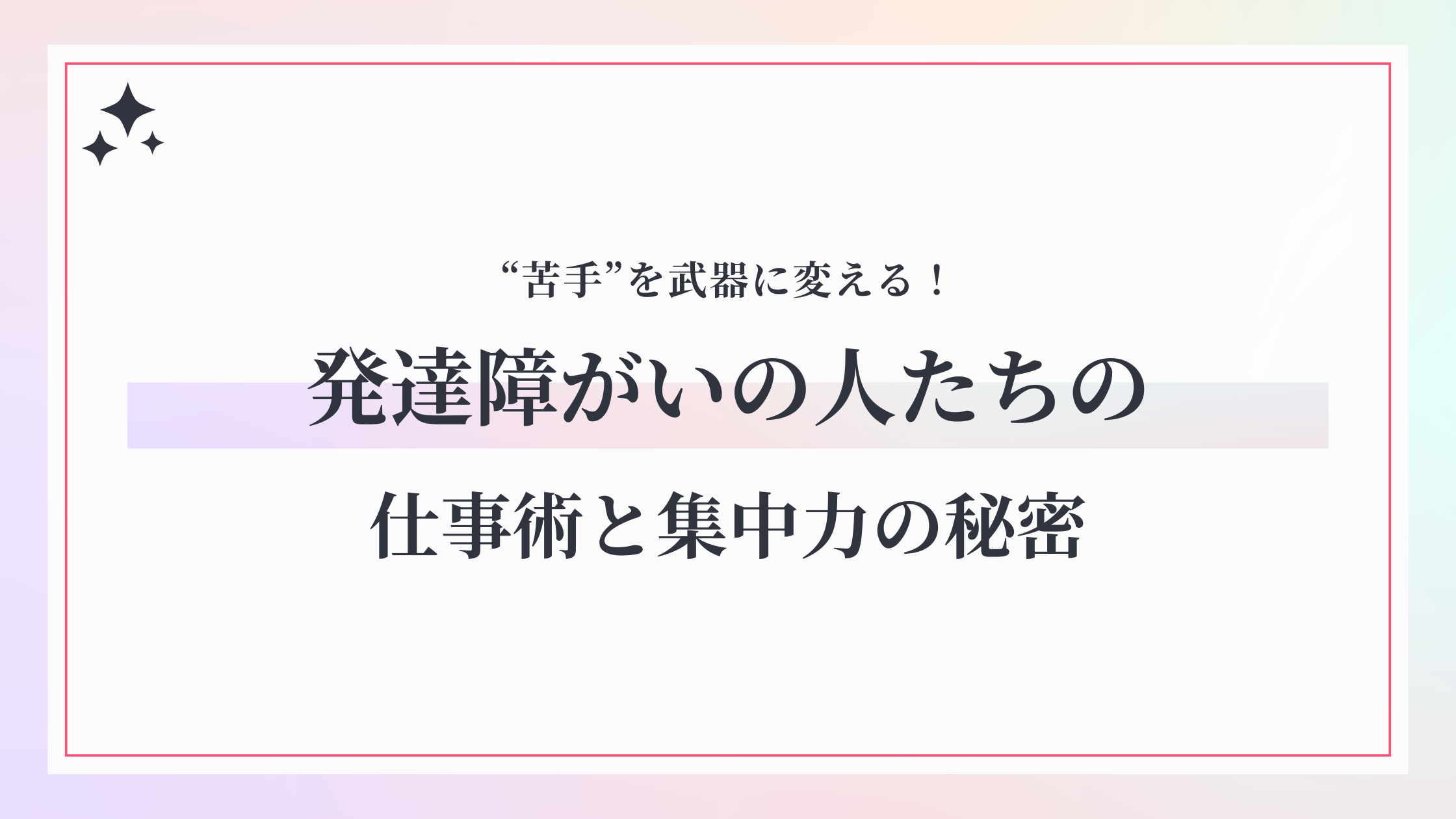発達障がいと「集中力」の関係を理解する

過集中(ハイパーフォーカス)という特性
発達障がい、とくにADHDやASD(自閉スペクトラム症)の人には、「過集中」と呼ばれる特性があります。
これは「好きなこと」「興味があること」に対して、周囲の音や時間を忘れるほど深く没頭できる力のことです。
一般的には「注意散漫」「集中が続かない」と思われがちですが、実際には“特定の対象への異常なほどの集中”という、両極端な特性があるのです。
例えば、プログラミングに没頭して気づけば朝になっていたり、趣味の研究に取り組んで数時間が一瞬で過ぎていた、という経験を持つ人も少なくありません。
これは単なる「欠点」ではなく、適切に活かせば社会において大きな力となるものです。
「好き」をエネルギーに変える
過集中は「嫌いなこと」には発揮されにくい一方、「好きなこと」には大きな成果を生み出します。
つまり、自分の興味や関心の方向を見つけることが、才能を活かす第一歩となります。
厚生労働省の調査でも、発達障がいのある人が自分の強みを生かせる職場環境にいるとき、就労継続率が高い傾向があると報告されています。
参考リンク:厚生労働省「経営の観点から見た障害者雇用の効果と進め方」
発達障がいの強みが発揮される分野

IT・クリエイティブ分野での力
プログラミング、デザイン、動画編集、音楽制作などの分野では、細部に没頭できる力が活きやすいです。
コードのバグを探す、映像を丁寧に編集する、音を重ねて理想の音楽を作るといった作業は、まさに「集中の天才」の力が試される場です。
YouTubeには、発達障がいのあるクリエイターが自分の強みを活かして発信している例も多くあります。
研究・学問分野での成果
発達障がいのある人の中には、特定の分野に関する膨大な知識を蓄え、専門家顔負けの洞察力を持つ人がいます。
歴史、昆虫、宇宙、数学など、一見マニアックに思える知識が、研究分野や教育の場で大きな武器になることもあります。
ビジネスや企画の場での発想力
一方向に集中するだけでなく、独自の視点から新しいアイデアを生み出すことも強みです。
固定観念にとらわれず自由に発想できることは、イノベーションの源泉でもあります。
強みを活かすための環境づくり

自分に合った働き方を見つける
発達障がいの特性を理解したうえで、自分が成果を出しやすい働き方を模索することが大切です。
例えば、リモートワークやフレックス制度は、自分の集中が高まる時間帯に作業できるというメリットがあります。
近年では「就労継続支援」や「特例子会社」など、発達障がいの特性を理解した職場も増えています。
参考リンク:発達障害者支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)
周囲とのコミュニケーションを工夫する
強みを活かすには、周囲の理解も欠かせません。
そのために有効なのが「アサーション(自己表現)」です。
「自分はこの環境だと力を発揮しやすい」「この作業は得意」など、具体的に伝えることで、周囲との協力体制が生まれます。
参考リンク:自分でできるアサーショントレーニング(国分寺イーストクリニック)
休むことも“才能を活かす力”
過集中は疲労に気づきにくいため、休むことを意識的に取り入れることも必要です。
ポモドーロタイマー(25分集中+5分休憩)などを活用し、心身を守りながら長く才能を活かせる環境を整えましょう。
事例紹介:発達障がいと強みの活かし方

芸術家やクリエイターの例
世界的に有名な画家のゴッホや音楽家のモーツァルトは、発達障がいの特性を持っていたのではないかといわれています。
彼らの作品に宿る圧倒的な独創性は、「集中」と「こだわり」が生み出したものです。
現代日本でのロールモデル
近年は、日本でも発達障がいを公表しながら活動する著名人が増えています。
タレントの栗原類さんは、発達障がいを公表しつつ俳優・モデルとして活躍しています。
彼の著書『発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由』は、多くの人に勇気を与えています。
参考書籍:発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由(栗原類)
まとめ :発達障がいの強みを社会で輝かせるために
発達障がいは「できないこと」に焦点を当てられがちですが、実際には「集中の天才」ともいえる強みを持っています。
自分の興味・関心に基づいた分野を見つけ、環境を整え、周囲に伝えることで、その強みは社会の中で輝きを放ちます。
障がいは「個性」であり、視点を変えれば大きな可能性に満ちています。
一人ひとりの「集中の天才」が認められ、社会の中で活かされる未来を築いていくことが、私たち全員にとっての希望になるでしょう。