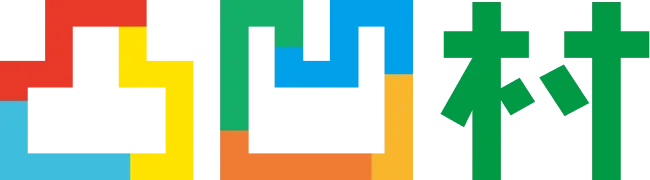「ひとりで暮らしてみたいけれど、サポートも必要」
そんな想いを抱える障がいのある方にとって、グループホームは“自分らしく暮らす”ための有力な選択肢です。
本記事では、グループホームの基本知識から、タイプごとの違い、入居までのステップ、費用の目安、実際の選び方まで詳しく解説します。
実際に制度を利用する人だけでなく、家族・支援者にとっても参考になる内容です。
「安心できる場所で、自立を目指したい」――そんな願いを叶えるための第一歩として、ぜひこの記事を読んでみてください。
グループホームの種類と特徴

① 介護サービス包括型
- 主に夜間・休日に食事・入浴・排せつ支援あり。
- 利用者数・事業所数とも最多で、軽度〜中等度の障がいの方に多く選ばれます
② 外部サービス利用型
- 主に夜間に相談や日常生活上の援助を提供。身体介護は外部の居宅介護サービスに委託。
- 比較的軽度の方に向いており、費用は場合により高くなることも。
③ 日中活動サービス支援型
- 平日昼間もスタッフ支援あり。医療的ケアや短期入所対応が特徴。
- 重度の障がいがある方にも対応可能になった新型サービス。
④ サテライト型住居
- グループホーム近くのアパートやマンションで生活。定期巡回支援あり。
- 将来の一人暮らしを見据える人に適しており、利用期限2年。
最新トレンド情報
動物との共生型ホーム
- 犬や猫と暮らすことで、情緒安定やQOL向上につながると報告例あり。
- 全国で60カ所以上が確認されています。
IoT・見守り技術の導入
- 転倒自動検知センサー、健康状態の遠隔モニタリングなどで安心感がアップ。
オンライン医療連携
- 医師との遠隔相談や服薬指導が可能で、通院負担も低減されています。
利用者にとってのメリット

①「ちょうどいい距離感」で暮らせる安心感
一人暮らしの自立性と、実家暮らしの安心感。
グループホームは、その“ちょうど中間”のような存在です。
- 食事や掃除などを自分でやりながら
- 必要なときはスタッフに助けてもらえる
- 他の入居者との関わりも、自分のペースでOK
②「少しずつできることが増える」自信につながる
日常生活そのものが、生活スキルのトレーニングになります。
- ゴミ出し、洗濯、買い物などを練習できる
- スタッフが必要なところだけそっと支援
- 簡単な料理や金銭管理にも挑戦しやすい
自分のペースで“できること”が増えるたびに、自信が育っていく。
一人暮らしへのステップアップを目指す人にもぴったりです。
③ 経済的な負担が少ない暮らし方
公的制度を活用することで、費用の不安を抑えられます。
- サービス利用料:原則1割負担(上限あり)
- 家賃補助(1〜2.5万円)で実質家賃が下がる
- 食費・光熱費も定額制で管理しやすい
地域によって補助の内容が異なるため、市区町村の福祉課で事前確認がおすすめです。
選び方のステップガイド

STEP 1|自分のニーズを整理しよう
まずは「自分がどんな暮らしを望んでいるか」を具体的に言葉にしましょう。
支援者や家族と一緒に整理するのもおすすめです。
- 夜間もスタッフにそばにいてほしい?
- 食事や入浴に介助が必要?
- にぎやかな環境より静かなほうが落ち着く?
- 将来は一人暮らしを目指している?
- どのくらいの距離で家族・支援者と関わりたい?
自分に合う支援のタイプを知ることが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。
STEP 2|支援区分と類型を確認しよう
障がい支援区分(0〜6)は、どの類型のホームを利用できるかに影響します。
| ホームの種類 | こんな人におすすめ |
|---|---|
| 介護サービス包括型 | 生活全般にわたって支援が必要な人 |
| 外部サービス利用型 | 生活は自立しているが、相談や見守りが欲しい人 |
| 日中サービス支援型 | 日中の見守り・支援が必要な人 |
| サテライト型 | 将来の単身生活を目指す人、静かな環境を希望する人 |
STEP 3|費用の見通しを立てよう
グループホームの費用は、場所・支援の内容・家賃補助の有無で差が出ます。
月額の目安(全国平均)
| 費用項目 | 相場(概算) | 備考 |
|---|---|---|
| サービス利用料(1割負担) | 5,000〜15,000円 | 障害福祉サービス費の1割 |
| 家賃 | 30,000〜50,000円 | 家賃補助により実質負担減可 |
| 食費・光熱費等 | 25,000〜35,000円 | 定額制のところも多い |
特定障害者特別給付費(補足給付)
家賃のうち上限1〜2.5万円まで国が負担。さらに市区町村で独自の助成がある場合も!
STEP 4|複数のホームを見学・体験しよう
パンフレットや写真だけでは分からない“雰囲気”や“肌感覚”を確かめましょう。
見学時のチェックポイント
- 室内のバリアフリー化(段差、手すり、トイレの広さなど)
- スタッフの対応は丁寧か?急かすような態度はないか?
- 利用者の様子は落ち着いているか?年齢層や性別構成は?
- 食事は手作り?外部委託?内容・栄養バランスは?
- 緊急時(発作、転倒など)の対応体制は?
可能であれば「体験入居」をしてみましょう。
数日でも過ごしてみると、生活の合う・合わないがよく分かります。
STEP5|サービス等利用計画を作成しよう
正式に利用するには、「サービス等利用計画」が必要です(※相談支援専門員が作成します)。
内容に含まれるもの:
- どのような暮らしを望んでいるか(将来像)
- グループホームでどのような支援を受けたいか
- 医療・就労・日中活動などとの連携方針
「自分の想い」をなるべく具体的に伝えましょう。
支援内容に反映されやすくなります。
STEP6|契約・入居準備をしよう
契約前に「重要事項説明書」を受け取り、内容をよく読みましょう。
施設によっては保証人や身元引受人が必要になる場合もあります。
入居前に準備するもの
- 印鑑(実印)と本人確認書類
- 生活用品(衣類、寝具、日用品など)
- 医療・服薬関係の情報(お薬手帳、通院記録)
- 緊急連絡先や支援機関の連絡表
STEP7|入居後の振り返り
入居後は6か月ごとに支援内容を見直す「モニタリング」があります。
スタッフや相談支援員と一緒に、現状を振り返って改善点を話し合いましょう。
モニタリングで確認すること
- スタッフの支援内容は十分か
- 他の利用者との関係でストレスがないか
- サテライト型や単身生活への移行希望はあるか?
不満や困りごとは遠慮せず伝えましょう。
状況に応じて、別のグループホームへの変更も可能です。
よくある質問
Q. 支援区分が「非該当」でも入居できますか?
A. はい、制度上は可能ですが、実際には断られることが多いです。
- 制度上、「非該当」や「区分1〜6」の人すべてがグループホームの利用対象です。
- ただし、ホーム側は国からの報酬(給付費)を収入源とするため、「非該当」や「区分1」の場合、報酬が少なくなるため、入居を断られることがあります。
- また「区分なしでも利用可能だが自己負担が高額になる」(区分認定されていないとサービス利用料が利用者負担になる)という実態もあります
Q. ASD・ADHDなど発達障がいだけでも利用できますか?
A. はい、発達障がいのみでも問題なく利用できます。
- 発達障がい(ASD・ADHD・LD含む)単独で入居できるホームは増えており、「発達障がい専門グループホーム」も存在します。
- 実際、重度の発達障がい者も対応可能な「日中活動支援型ホーム」などもあり、単なる施設入所より柔軟な選択肢があります。
参照:株式会社キズキ 発達障害のある人のグループホーム利用まとめ
Q. 支援区分が高すぎても入居できない場合がありますか?
A. 支援区分が高すぎると、サポートが不足する場合があります。
- ホームによって受け入れられる支援区分に上限があり、高度な支援(例:区分6など)が必要な場合は、対応できるスタッフ数やスキルを備えていないケースもあります。
- こうした場合は、「日中サービス支援型」や「介護包括型」、「施設入所支援」など高支援体制の類型を選ぶ必要があります。
参照:しゃふくさん
Q. 医療的ケアが必要でも利用できますか?
A. できますが、ホームの選び方が重要です。
- 日中サービス支援型や、医療連携が可能なホームであれば、看護師巡回やオンライン診療などで対応できます。
- 医療依存度が高い場合、「施設入所支援(障がい者支援施設)」も含めて複数の選択肢を検討するのが望ましいです。
参照:SMILE HOUSE
まとめ:理想の暮らしを形にするために
- 自分の「欲しい生活」を明確に
- 類型の違いを理解し、マッチするものを選ぶ
- 見学で「肌感覚」を確認
- 支援計画と費用の見通しをしっかり持とう
グループホームは「暮らしの安心」と「自立支援」の両方を可能にする住まいです。
見学や関係機関との相談を重ね、あなたらしい毎日が送れる居場所を見つけてください。
関連記事