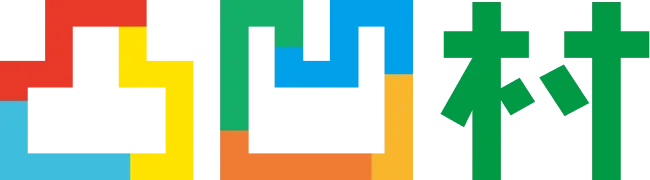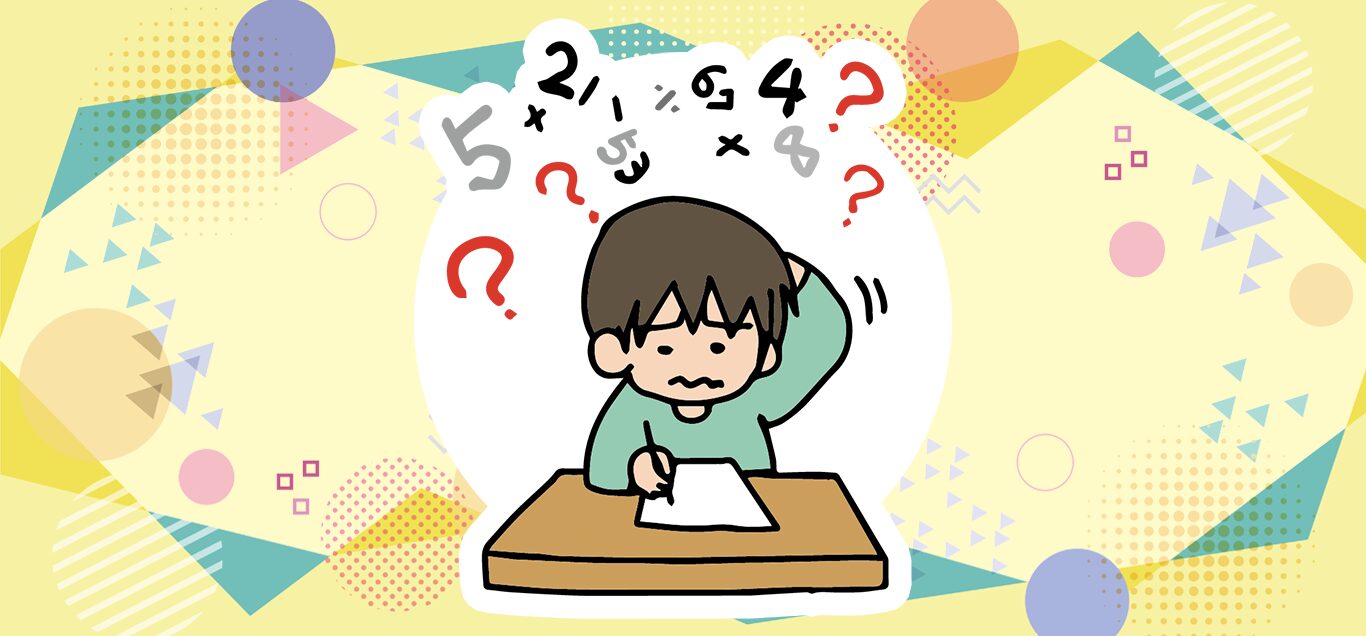「発達障がいグレーゾーン」の存在について、専門医が「発生割合が増えているわけではない」と感じる理由は、発達障がいの特徴が明確に定義されていないことにあります。精神科医の岩波明さんによれば、「発達障がいの症状の区分には客観的な指標が存在せず、個人差も大きい。専門医であっても診断に悩むことは多い」とのことです。
誤解が広まった理由
「発達障がい=自閉症」という誤解が広まった理由は、まず、診断名にあります。かつて、自閉症はDSM-Ⅳ-TRにおいて「広汎性発達障がい(PDD)」に含まれていました。このため、発達障がいと聞けば自閉症を指すという誤解が生じました。
また、日本の発達障がいの診療が長い間、自閉症を中心に行われてきたことも大きな要因です。この傾向が、発達障がいを自閉症と同義とみなす誤解を生み出しました。このため、一般の人々や医療関係者の中にも、「発達障がい=自閉症」という誤解が根強く残っているのです。
自閉症は医学界で「研究し甲斐のある」疾患とみなされてきました。なぜなら、自閉症はしばしば「強度行動障がい」を示し、他の児童期の精神疾患よりも治療や対応が難しいとされるからです。
強度行動障がい
強度行動障がいとは、自分の体を叩いたり、食べられないものを口に入れたり、壁をドンドン叩いて壊したり、他人を叩いたり、大泣きが何時間も続いたり、急に道路に飛び出したりする行動を指します。
これらの問題行動は、本人の健康を損なうだけでなく、周囲の人々の生活にも影響を及ぼすため、特別な支援が必要です。岩波さんが診療した患者さんの中には、「信号機を見ると必ず石を投げる」という特異な行動特性を持つ方もいました。
自閉症
自閉症は治療が難しく、鎮静化させる薬はあっても治療薬は存在しません。そのため、精神科に長期入院するケースも珍しくありません。このような背景から、日本では自閉症、特に知的障がいを伴うケースを診療の中心に据えてきました。さらに、教育界でも自閉症の治療教育に関する多くの研究が行われています。
世界的にも自閉症に対する関心は高く、自閉症や関連症状については積極的な研究が行われています。自閉症は多くの謎を含む疾患であり、その研究は未だ多くの進展を遂げています。
また、自閉症の人々には「サヴァン症候群」と呼ばれる特異な能力を持つ人も多く見られます。これらの人々は、驚異的な記憶力や再現力を持ち、その脳内システムに関する研究が盛んに行われています。各疾患には明確な境界線が存在しないというのが現在の医学の見解です。
ケースバイケースでの考察が求められる
ASD、ADHD、LD(読字障がい、書字障がい、算数障がい)、トゥレット症候群、サヴァン症候群などの区分は、あくまで現在の知見に基づくものであり、厳密な境界線を区別するものではありません。実際には、これらの疾患の特徴を併せ持つ例も多く存在し、異なる疾患の間には類似点も見られることから、一つの疾患としてではなく、ケースバイケースでの考察が求められます。
さらに、個別の疾患においても、症状の濃度には幅があります。同様の特徴を持っていても、一部の患者は比較的社会生活が可能な場合もありますが、他の患者は引きこもりを続けることもあります。実際、米国精神医学会のDSM改訂では、「PDD(広汎性発達障がい)」というカテゴリーが「ASD(自閉症スペクトラム障がい)」として変更された際に、「症状と症状の間に明確な境界線は引けない」という考え方が示されています。
「ADHD症状が明確だがASD症状もある」というケースは、その患者ごとに個人差が大きいことを示しています。このような状況は、各疾患の特徴がスペクトラム状に広がっており、境界線や範囲が明確ではないことを表しています。
実際に、患者さんを診察すると、単一の病名で説明できない場合がしばしばあります。例えば、ADHDの特徴が明確に見られる一方で、ASDに類似した対人関係の障がいも示す患者もいます。